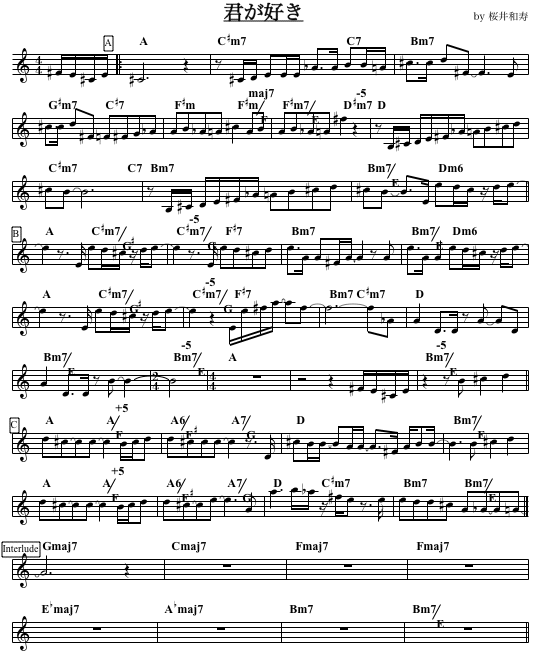
| 目次 | 前話 | - |
 |
||
今回、取り上げるのはミスチルことミスター・チルドレンの「君が好き」。実は「ミスチルの「君が好き」をアナライズしてください。」というメールをいただき、今回取り上げてみました。
イントロのあと、A(10)-B(10)で1コーラス。2小節のつなぎに続いてA(10)-B'(10)-C(8)、間奏が8小節あって、最後はBを繰り返す。Bがいわゆるサビ。Cは大サビなんて言われる、一回しか出てこないメロディ。ただ、通常の大サビは転調することが多いが、この曲ではキーはイ長調(Aメジャー)のまま。サビの続きというニュアンスが強い。むしろ間奏が大サビのイメージに近い。なお、1コーラス目のBの最後は4分の2拍子、つまり2拍があるが、流れ上はそれほど重要ではない。
Aメロが始まってすぐの2小節目。コードがC#m7-C7-Bm7と半音下降するところ。
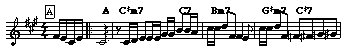
理屈をこねれば、C7はBm7の半音上の7thということで、F#7のウラコードとも言える。だからC#m7-F#7-Bm7と機能的には同じということになる。
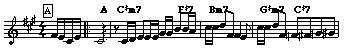
しかし、笑っちゃうほどハマらない(^_^;)。ここは単純に半音下降と考えるのが正解なんじゃろうな。半音下降に意味があるため、仮にC7がCm7になってもほとんど区別出来ない。
8小節目にもう一度登場する、この3度マイナーから半音下降して2度マイナーに行く進行は、結構いろんな曲で使われておる。例えばビートルズの「If I Fell」なんかがそうじゃ。
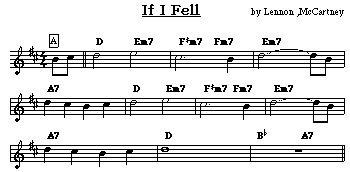
そのほか、ビートルズでは「Do You Want To Know A Secret」なんかもそうじゃな。
覚えておいて、みんなで使おう!
Aの5小節目。F#7からルートが半音下降するところ。
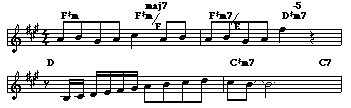
よく「クリシェ」なんて言われる進行じゃ。「クリシェ」は慣用句という意味じゃが、厳密な定義はよくわからない。元の和音の構成音の一部をちょこちょこと動かすみたいなニュアンスかのう。実はこの曲には3つの「クリシェ」が登場する。
1つ目の「クリシェ」はトニック・マイナーからルートが半音下降するパターン。上に書いたコード名はその結果を無理無理コード名にしたもの。4つ目のD#m7-5は普通、F#m7だったりする。
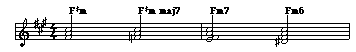
実はD#m7-5とF#m6は構成音が同じ。

まあ、どうでもよかったんじゃが、D#m7-5は「ズージャでGO!第3部第8話」で紹介した「魅惑のハーフ・ディミニッシュ」。つまりサブドミナントの半音上で、次にサブドミナントへ進行していることから、こんな表記にしてみました。
ちなみにF#m7の前のG#m7-C#7はII-V(ツーファイブ)じゃが、普通はG#m7-5-C#7。5度(レ♯)をフラットしないことによる「ちょこっとアウトサイド」がいいのよね。
このクリシェはマイナーの曲では冒頭に使われることが多く、例えば「マスカレード」なんかがそうじゃ。

サビに入る前のDm6。意外なコードだし、サウンド的にも「アレ?」と思わせる。
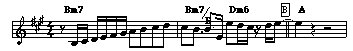
しかしこれはかなり理論的に説明出来る。Dm6はサブドミナントであるDのマイナー。D-Dm6」という進行は定番中の定番じゃが、実はサブドミナント・マイナーにはドミナントの代理コードというもう一つの顔がある。
「ズージャでGO!第3部第3話」で「マイ・ウェイ」を例に引いて説明したが、用法はそれと同じ。ドミナントの代理というと、「E7とDm6は同じなのか?」と思われてしまいそうだが、構成音ももちろんサウンドも全然違う。Dm6には「ファ」と「シ」の間に「トライトーン(三全音)」という不安定な音程があって、それがトニックへの解決引力を生むなんて説明される。なんのこっちゃ!、という感じじゃろうね。詳しく説明し出すと「音の周波数の比」みたいな話からしなくちゃいけないし、わしもよくわからんのでここでは割愛。機能的に「E7≒Dm6」とだけ覚えておこう。
Bm7/EはE7の「ドミナント臭さ」を消す定番コード(ズージャでGO!第3部第6話参照)。E7に含まれる「ソ♯」ー「レ」間のトライトーンがないのがポイントじゃが、その次に機能的にE7に等しいDm6をもってくることで、トニックのAに解決している。こういう使い方は結構、珍しい。
ただ、このアイディアは作曲者によるものなのか、アレンジャーによるものなのかは定かではない。
サビの冒頭、Aのルートが半音下降するところ。これが2番目のクリシェじゃ。
トニック・メジャーのルートがダイアトニックに、つまり音階に従って下降するパターンとしては「Everything」を以前に紹介したが、こちらは半音づつ下降する。
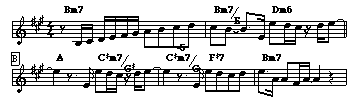
コード進行としてはI→IIIm7→IIIm7-5→VI7で、IIIm7-5→VI7はIIm7-5であるBm7/EへのII-V(ツーファイブ)なんじゃが、ルートの半音下降がトニックからVI7-5への進行をスムーズにさせているわけじゃ。
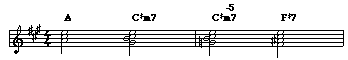
Cに登場するAの5度が半音上昇するところ。これが3番目のクリシェ。

上記2つのクリシェほど頻繁には使われないが、ジョン・レノンの「Standing Over」あたりが一番有名かしら。古いところではデイブ・クラーク・ファイブの「Because」の冒頭(誰も知らない?)。松田聖子ちゃんの「Sweet Memories」のサビは似てるようで、ちょと違う。
トニックの5度(ミ)を半音ずつ上げていって、7度(ソ)まで行って、サブドミナントに進行するのがこのクリシェの目的。つまりA7→Dという進行になるわけじゃ。この曲ではルートを工夫して、2番目以降は半音ずつ上昇する音をルートに持ってきているが、基本は一緒。
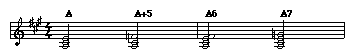
2番目のA+5はAaugなんて書く場合もあるんじゃが、「ラ−ド♯−ファ」の各音程が長三度で12音階を三等分してる、なんて突然書いてもわからんかのう(^_^;)。12÷4=3ということなんじゃが...詳しくは「ズージャでGO!第3部第7話」を見てください。この曲には特に関係ないけど。
3番目のA6は実はF#m7と構成音は一緒。
![]()
「じゃあ、A6/F#なんて書かずに、F#m7って書けばいいじゃん」と言われそうですが、まあ、確かにそうなんだけど、半音ずつ上昇してる、ってことを強調したくてね。
ホイットニー・ヒューストンには半音上昇2回連続、という曲がある。
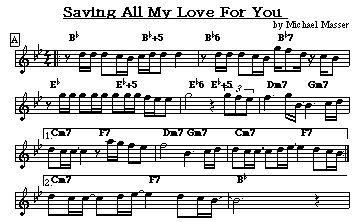
Bbで5度を半音上昇してEbになってからも半音上昇、という技じゃ。
先ほど、「Sweet Memories」のサビは似てるようでちょと違うと書いたのは訳がある。

(比較のため、キーを変えてあります)
実はこの曲でも聖子ちゃんが「ミ」が半音ずつ上昇するフレーズを歌っているし、最終的にサブドミナントに至るところも一緒なのじゃ。C#7とA+5は構成音はかなり近いし、A6とF#m7は同じとさっきも書いた。
![]()
にも関わらず、あえて「ちょと違う」と言ってるのはメロディの起伏の大きさに起因しているのじゃ。
比較のため、「君が好き」と「Sweet Memories」のメロディ・ラインを再掲しておこう。「君が好き」では1〜2小節目に登場する音は「シ」「ド♯」「レ」の3音だけじゃ。

それにくらべ「Sweet Memories」の1〜2小節目に登場する音は「ド♯」「ミ」「シ」「ラ」「ファ」「ファ♯」と多く、動きも激しい。

試しに「Sweet Memories」をクリシェ的なコード進行に変えてみよう。
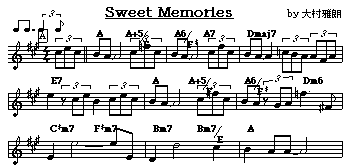
あんまり、変わらんかのう(^_^;)。まあ、起伏の激しいメロディには半音上昇のクリシェは地味過ぎて、マッチしないというところか。
「半音下降のクリシェではメロディの起伏が激しかったじゃない」という声が聞こえてきそうじゃな。そう、バックが下降する場合と上昇する場合ではフロントのメロディに与える影響が違うのじゃ。その件についてはまた、後日。
今回、「クリシェ、クリシェ」と安易に使ってきたが、本来は「クリシェ的なサウンド」もしくは「クリシェを発想の基本としてそこから導き出したコード進行」と言うべきなのかもしれない。「クリシェ」の基本は「装飾的」であることなのじゃ。
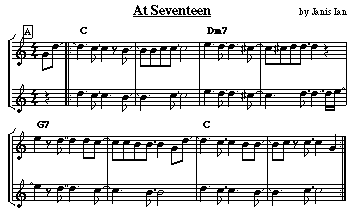
下段にクリシェ・ラインを載せてある。この曲のようにコードがCという中で、構成音を「レ−ド−シード」と動かすというのが本来のクリシェなんじゃなかろうか。これに無理矢理、コード名を付ければ以下のようにも書けるけど、ウザイよね。
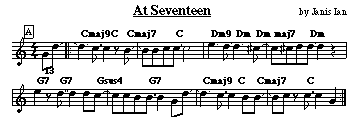
ところが次の例では「装飾的」じゃ済まなくなっている。

Dm7の5度が半音上昇してD7に至り、Gm7に進行するパターンじゃが、この場合は「装飾だから」とDm+5やDm6を省略するわけにはいかないじゃろう(さすがにD7は省略しないじゃろうがね)
大胆に言っちゃえば「次のコードに影響しないのがクリシェ、次のコードに影響するのがクリシェ的」ってとこか。もう一つ、例を見てみよう。ジャズマンなら誰でも知ってる「酒バラ」じゃ。
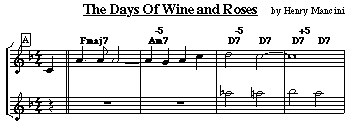
3〜4小節でD7の5度であるラを「ラ♭−ラ−シ♭」と動かしているが、こういうのが本来のクリシェ。クリシェの考え方を応用して1〜2小節を変えたのがこれ。
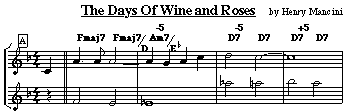
こっちはFmaj7とD7のつなぎに「ファーミーミ♭」というクリシェを応用している、「クリシェ的」なコード進行と言えないだろうか。
ちょっと脱線しちゃいましたね。失敬。
実はポイントその3以外、個人的興味はなかったんだけれど、今回コピーしてて一番、「ふむふむ、なるほど」と関心したのが、サビの最後。ところが、肝心のコピーに自信がなく、わしの勘違いかもしれないので、ポイントとして挙げられなかった。わしの耳にはこう、聞こえたんじゃ。
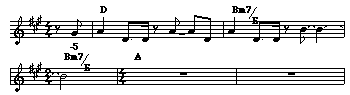
Bm7/EはE7のトライトーン抜きコード。続くBm7-5/Eも同様にトライトーン抜きじゃが、ファ♯がファになってるのがポイント。結果的にE7-9(E7thフラット9th)に近いサウンドになっている。
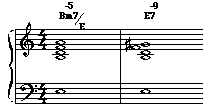
Bm7/Eは「ミ」と「ラ」の間の完全4度音程がキモじゃが、Bm7-5/Eでも「ミ」と「ラ」は存在している。E7-9じゃと「ラ」じゃなく「ソ♯」になるので、完全4度音程は存在しない。
「どっちも大して変わらないじゃん」と言われそうじゃ。確かに対して変わらない(^_^;)。どうでもいいことなんじゃが、「Bm7/E→Bm7-5/E」という進行がアリなんだ、ということを知ったことに価値があるのじゃ。たとえミスチルがそうやっていなかったとしても、ね。
音を採ってて一番難しかったのはボーカル。細かい音が多くて、とても全部を再現するにはほど遠い出来じゃ。ここは是非、本物を聞いて下され。アルバムでは「It's A Wonderful World(TFCC-86106)」に収録されています。
これからもリクエストがあったら、どんどんお寄せ下さい。10曲に1曲くらいは取り上げるかも(^_^;)