| 以前に博士に勧められて聴いた「Giant Steps」にひろ子はびっくり。この曲の秘密を博士に教えてもらおうと... |
| ひろ子: |
博士、「Giant Steps」って凄い曲ですね。何がなんだかわからないけれど、格好よくて、頭の中がグワングワンするような感じです。どうなってるのか、教えていただけますか? |
| 五反田: |
「Giant Steps」はジャズ史上最大の難曲とも言われるが、またジャズの歴史を塗り替えた、非常にエポックメイキングな曲でもある。ただ、いきなり「Giant Steps」じゃあ、話が難しくなるので外堀から説明していこうか。
ひろ子くんはWeather Reportの「Teen Town」という曲を知っておるかな?
|
| ひろ子: |
こんな曲ですよね?
コードはC7 - A7 - F7 - D7の繰り返しだと思うんですが、よくわからないコード進行ですね。
|
| 五反田: |
今までII-V(ツー・ファイブ)とかウラ・コードとかいろいろ説明してきたが、このコード進行はどうにも説明できないなあ。というか、実は、説明できない、なるべく繋がりがないようにしたコード進行だとも言える。 |
| ひろ子: |
「繋がりがないコード進行」ですか? |
| 五反田: |
そうじゃ。5度圏(4度圏)を覚えておるな? 例えばDm7 - G7 - Cmaj7という進行のルートを5度圏(4度圏)上に表してみるとどうなるかな? |
| ひろ子: |
こういう感じでしょうか?
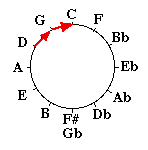
|
| 五反田: |
こそれじゃあ、Em7 - A7 - Dm7 - G7のIII-VI-II-V(3−6−2−5)だとどうなるじゃろうか? |
| ひろ子: |
Em7 - A7 - Dm7 - G7はこうですね。
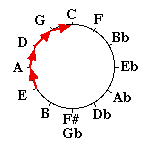
|
| 五反田: |
それじゃあ、「Teen Town」のコード進行を5度圏(4度圏)上に描くとどうなる? |
| ひろ子: |
C7 - A7 - F7 - D7なので、こうでしょうか。随分変な形になりますね。
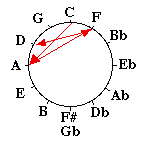
|
| 五反田: |
考えてみれば当然のことなんじゃが、II-V-Iというコード進行は5度下行(4度上行)なわけで、5度圏(4度圏)上では隣のルートに進行することになる。それ以外の例えば「C7 - A7 - F7 - D7」なんていう5度進行(4度進行)ではないコード進行が5度圏(4度圏)上でいびつな形になるのは当たり前なんじゃ。
あえて言えば「C7 - A7」がそのまま4度上がって「F7 - D7」になっている、ことぐらいは判るじゃろうが。
|
| ひろ子: |
あっ、確かにそうですね。でもそれだけじゃあ、もうひとつですね。 |
| 五反田: |
そこでじゃ、5度圏(4度圏)に変わって半音圏というものを考えてみよう。
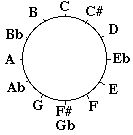
|
| ひろ子: |
「右回りだと半音ずつ上がって、左回りだと半音ずつ下がっていくんですね。これだとどういうことが判るんですか?
|
| 五反田: |
試しにDm7 - G7 - Cmaj7やEm7 - A7 - Dm7 - G7 - Cmaj7のルートの動きを半音圏上に描いてみなさい。 |
| ひろ子: |
こうなりました。
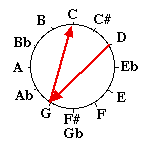 |
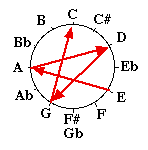 |
| Dm7 - G7 - Cmaj7 |
Em7 - A7 - Dm7 - G7 - Cmaj7 |
Em7 - A7 - Dm7 - G7 - Cmaj7は星形(☆)..ちょっと違うか。
|
| 五反田: |
そもそも星形(☆)は正五角形の点を結ぶのじゃから、12音階上では作れんよ(^_^;)。
もう少し練習問題でディミニッシュ・コードの構成音とホール・トーンスケールの音を描いてみよう。
|
| ひろ子: |
ディミニッシュは短3度ずつ音を積み重ねて行くんだったし、ホール・トーンは全音ずつ上がっていくんだから...
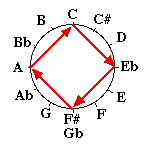 |
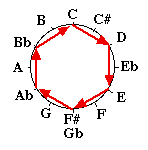 |
| Diminishコード |
ホール・トーン |
あ〜、きれいな形になりましたね。デミニッシュは正三角形だしホール・トーンは正六角形です。
|
| 五反田: |
この「きれいな図形になる」ことがポイントなんじゃ。Dm7 - G7 - Cmaj7などでは正三角形にならなかったじゃろう。
それはCの引力によって図が歪められたと考えるといい。つまりD、G、Cは均等な力関係ではなく、Cを主人とした家来にDとGがいるとイメージしなさい。
|
| ひろ子: |
...はい(^_^;) |
| 五反田: |
ところがディミニッシュやホールトーンでは全ての音が均等な力関係にある。すなわち、主従関係がないのじゃ。だから正多角形になる。 |
| ひろ子: |
...(ちんぷんかんぷん) |
| 五反田: |
そこで「Teen Town」のコード進行を半音圏に描いてみるとこうなる。
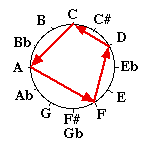
|
| ひろ子: |
台形みたいになりましたね。正方形にはなりませんでしたけれど... |
| 五反田: |
それでもII-V-Iなどよりも角度が大きいじゃろう。コードとコードの力関係が対等に近いと考えていい。 |
| ひろ子: |
コードの力関係が均等だとどういうことになるんですか? |
| 五反田: |
いわゆる安定感(終止感)が希薄になる。トニックと呼べる強い引力を持ったコードがないので、トーナリティ(調性)が曖昧になり、音楽が不安定になる、まあ、それだけ響きも近代的になるというわけじゃ。 |
| ひろ子: |
そうすると当然、アドリブをとるのも難しくなりますよね。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ。ジャコくんはその辺を考慮して若干、図形を歪めて、つまり少しだけCの力を強くしたのかもしれん。ところがコルトレーン大先生の「Giant Steps」はきわめて幾何学的な造りになっておるのじゃ。 |
| ひろ子: |
ジャイアント・ステップスはこういう曲でしたよね。
ツー・ファイブやドミナント・モーションもあって、一見普通の曲なんですが、この曲のどこが幾何学的なんでしょう?
|
| 五反田: |
この曲の転調がどうなっているのか、わかるかね? |
| ひろ子: |
「D7-G」でキー=G、「Bb7-Eb」はキーがEb、「Am7-D7-G」はキーがG...こんな感じでしょうか?
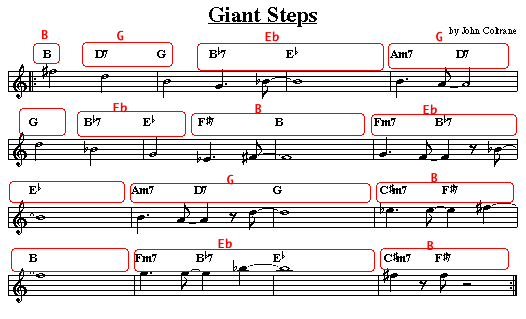
キーの移り変わり
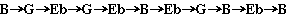
|
| 五反田: |
これを先ほどの半音圏に描いてみるとこのようになる。
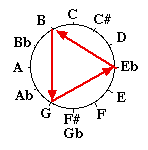
|
| ひろ子: |
見事な正三角形になりました。ということは、つまり...3つのキーが均等な力関係ということですか? |
| 五反田: |
そうなんじゃ。だからどのキーに転調しても距離感が同じなので、特別な緊張感もなければ安定感もない。常に3つのキー上を浮遊しているような感じを受けるんじゃ。
またB→G、G→Ebなんていう転調ひとつひとつをとってみても、あまり例がない珍しい転調なんじゃ。B、G、Ebを同時に弾くとオーギュメントになるじゃろう。
|
| ひろ子: |
でもこんな早い曲で頻繁に転調があって、しかもその転調が普通じゃないんじゃ、アドリブを取るのは無茶苦茶、大変なんじゃないですか。それをコルトレーン先生はやってしまうなんて、凄すぎる! |
| 五反田: |
確かにコルトレーンのこの演奏は凄いが、ものすごく練習したのじゃ。自分ばっかり練習して、自分の演奏がよければピアノが途中で弾けなくなっても平気でアルバムに入れてしまうわけじゃ。 |
| ひろ子: |
まあ、なんて自分勝手な! でもそれがジャズなんですよね。
それにしてもこの曲じゃテンションとか考えてる余裕もないです。
|
| 五反田: |
というか、テンション使ってる暇がないというか、意味もないというか。テンションを使ったフレーズなんぞを弾いていたら、頻繁に変わるトーナリティ(調性)が曖昧になってしまい、元も子もなくなるじゃろう。その証拠にコルトレーンもほとんどダイアトニックのフレーズに終止しており、多くはコードトーンでフレーズを作っておる。 |
| ひろ子: |
たとえばここですね。
テンションと言えるのはD7のフラット9thくらいで、それ以外はダイアトニックスケールやコードトーンがほとんどです。
第3部第4話で博士が教えてくれたダイアトニック・スケールをドミナントから下ってくるフレーズも使ってます。かなりシンプルなフレーズが多いですよね。
|
| 五反田: |
こんなのも頻繁に使っておったな。とっても基本的なツー・ファイブ・フレーズじゃが、それだけにトーナリティ(調性)を明確に表すには最適じゃ。
でもやっぱり特徴的なのは1〜3小節や5〜7小節の2拍ずつコードが変わるところじゃ。
|
| ひろ子: |
曲の冒頭ということもあり、とっても印象的です。 |
| 五反田: |
このコード進行は「コルトレーン・チェンジ」とも呼ばれ、ターンバックなどにも使われる。
|
| ひろ子: |
とてもメカニカルな響きですよね。 |
| 五反田: |
だから、いわゆる「唄う」ようなメロディアスというか音楽的(?)なフレーズはピアノ・ソロの後にようやく出てくるくらいじゃ。
|
| ひろ子: |
これは私の勝手な感想なんですが、「Giant Steps」は何かエチュードのような感じがするんですが... |
| 五反田: |
その感想は実に正しい。「Giant Steps」は壮大なる練習曲なのじゃ。もちろん、コルトレーン本人が最初からそう考えたわけではないじゃろうが、結果的にコルトレーンのキャリアに於いて「練習曲」になった。 |
| ひろ子: |
それはどういうことでしょう? |
| 五反田: |
例えばコルトレーンは「But Not For Me」のようないわゆる「唄モノ」にもコルトレーン・チェンジを当てはめて演奏していた。
|
| ひろ子: |
これまた、随分と大胆にリハーモナイズしていますね。 |
| 五反田: |
通常、リハーモナイズはメロディが乗っかるように和音だけを変えるのじゃが、コルトレーンはテーマのメロディまで変えてしまう。これが許されるのはコルトレーンとDave Libmanだけじゃ。
「But Not For Me」以外にも「Body & Soul」のサビのターンバックに使っておったなあ。
その他には「Confirmation」のメロディをもとにした「26-2」なんていう曲もある。
で、こういう唄モノにもコルトレーン・チェンジが適用出来るとなると、シンプルなコード進行をコルトレーン・チェンジに変えてアドリブを取る、なんてこともアリになる。
|
| ひろ子: |
え? よくわかりましぇ〜ん! |
| 五反田: |
ブルースなどでもとのコード進行をコルトレーン・チェンジに置き換えるんじゃ。あんまりズバリの例が見つからないが、こんな風に。
|
| ひろ子: |
2段目のサブドミナント、コードだとEb7の箇所を「Eb7 - B7 - D7 - G7」に置き換えているんですね。
教則本なんかだとそのものズバリの例がありますよ。
|
| 五反田: |
ブルース以外でも、例えばコードが「G-C-G-C」という超ダイアトニックなサウンドに変化を付けるために、こんな風なソロをすることもある。
|
| ひろ子: |
キーが「F#-C#-A」とチェンジしたと想定しているわけですね。「C#-A」の転調が長4度下への転調で、コルトレーン・チェンジを感じさせます。 |
| 五反田: |
置き換えるコードはコルトレーン・チェンジに限らない。理論的にはうまく説明できないが、こんな例もある。
|
| ひろ子: |
アドリブの途中でソロイストが勝手にコード進行を変えちゃうわけですよね。バッキングしているピアノやベースは瞬時にそれにあわせてコードを変えるなんて不可能ですよね。そうするとソロイストとバッキングが違うコード進行で演奏することになって、音楽的に破綻してしまいませんか? |
| 五反田: |
微妙なところじゃな。破綻することもあるかもしれん。でも考えてみなさい。ソロのフレーズがバックのサウンドから離れると、とっても緊張感が増すじゃろう? それが上手にバックのサウンドに戻ってくるとほっとする。これこそ「解決」ではないか。 |
| ひろ子: |
第3部第5話で話していただいた「半音上やコンディミ」、第3部第6話の「ウラ・コード」なんかと考え方は一緒なんですね。 |
| 五反田: |
そうじゃ。言ってみればテンションを使う理由も同じじゃ。要は基本の流れとは異なるサウンドを出して緊張感を演出して、元に戻る、これが全てじゃ。 |
| ひろ子: |
そういう意味でもブルースや単純なコード進行の場面であれば、もとのトーナリティが明確なので、ちょっと外れたアウト・フレーズも違和感なく聴けるんですね。 |
| 五反田: |
ただ、いくらコルトレーンといえども、何の準備もなしに、もとのコード進行以外のコードを想定してアドリブするなんてことは難しい。
「Giant Steps」であの激しい転調をものにしたコルトレーンだからこそ、違う曲を演奏していても頭の中に自然とコルトレーン・チェンジが鳴っていたのかもしれない。コルトレーンはそれを徹底的に追及し、現代ジャズ・アドリブの方法論の一つとして確立したんじゃ。
だからあとから考えると「Giant Steps」はいい練習になった、というわけなんじゃ。
|
| ひろ子: |
ということはもしかして、私にもコルトレーン・チェンジをマスターして、自分のアドリブで使いなさい、って言おうとしてます、博士? |
| 五反田: |
全く、その通りじゃ。 |
| ひろ子: |
ひぇ〜、助けてくださいよ〜。あんな激しい転調をあのテンポで練習するのは辛すぎます〜。
|
| 五反田: |
まあ、いきなりは無理じゃろうから、地道に努力するしかない。 |
| ひろ子: |
ということはマイナス・ワンも「Giant Steps」だったりしますう?(^_^;) |
| 五反田: |
最初から速いテンポでやっても時間の無駄なので、今回はボサノバ仕立てでやってみよう。 |
| ひろ子: |
「Giant Steps」をボサノバで、ですか? |
| 五反田: |
ボサノバだと、それほどテンポが速くなくてもサマになるじゃろう。さあ、やるぞ!
|
| みなさんも嫌がらずに「Giant Steps」を練習しましょうね。 |
| つづく |