| 前回の解決の話をさらに広げていきましょう。 |
| ひろ子: |
前回、「解決」の話をしてましたよね。「緊張」から「安定」に移る課程が「解決」だと。それって第3部第2話で説明していただいた「ドミナント・モーションの力」にも通じてるんですよね?
また、第3部第1話では「ドミナントは次にトニックに「行きたい、行きたい」とムズムズしてる性質を持っている。」ともい言ってました。これってズバリ、「解決」のことですよね。
|
| 五反田: |
そうじゃ。話の展開上、半音上の話から唐突に解決の話になってしまったが、もともと「解決」というのはドミナント7thコードからトニック・コードに到達して安定化(終止感を得る)ことを指すんじゃ。 |
| ひろ子: |
そのドミナント7thのところでテンションとかを使って、カッコよく解決させるわけですね。 |
| 五反田: |
よく理論書なんかには「ドミナント7thには他の全ての音程に比較してもっとも不安定でトーナリティのはっきりしない三全音音程があり、それが半音進行で長三度音程を持つトニック・コードに進行して安定する」なんて書いてあるよね。
マイナーの場合は短三度に解決するんだけど。
|
| ひろ子: |
だからドミナント7thコードのボイシングの時には3度と7度の三全音音程(トライトーン)の2音+テンションを弾くわけですね。
|
| 五反田: |
その通りなんじゃが、逆に考えればテンションなしではトライトーンの引力が強すぎて、露骨過ぎる。つまり7th臭いんじゃ。テンションはその7th臭さを消す効果があるとも言える。
ジャズではもちろんじゃが、ポピュラー音楽でもその傾向が近年、顕著じゃ。例えばこんな曲でも、なにげなくテンションを使って7th臭さを緩和しておる。
のっけのメロディの「ファ」が「A7」のb13(フラッテッド13th)で、切なさを演出しておる。まさに「つかみはOK!」というメロディじゃな。
|
| ひろ子: |
なにもこの曲でなくても....例えば「I'm A Fool To Want You」とか。 |
| 五反田: |
これこれ! それは禁句じゃ(^_^;)。
ただ、ポップスなどの場合、テンションを使う例はそんなに多くないのは事実じゃ。その代わり、こんなサウンドで7th臭さを緩和しておる。このサウンドはもはや一般的といってもいいくらい、普及していて、あらゆる曲で頻繁に聞かれる。
何回も登場するGm7/Cというのがそれじゃ。
|
| ひろ子: |
本来、C7であるはずのところで使われているんですね。Gm7/Cというのはどういう和音なんですか? |
| 五反田: |
以前(第3部第2話)にも出てきたが、「ルート指定コード」といってルートをCにしてその上にGm7を弾くという意味じゃ。「Gm7 on C」と書いたりもする。
似たような表記で というのもあるが、こちらはDコードの上にCコードを弾くという意味で分数コードなんて言っている。本によって書き方がまちまちなので混乱するかもしれんが「ズージャでGO!」では次のように書くことにしよう。 というのもあるが、こちらはDコードの上にCコードを弾くという意味で分数コードなんて言っている。本によって書き方がまちまちなので混乱するかもしれんが「ズージャでGO!」では次のように書くことにしよう。
| 種類 |
表記 |
意味 |
| ルート指定コード |
 |
ルートにCを弾いて、その上にGm7を弾く |
| 分数コード |
 |
低音部にDコードを弾いて、その上にCコードを弾く |
|
| ひろ子: |
上の曲では、Gm7 - C7となるはずがGm7-Gm7/Cと上のコードは変わらずにルートだけ変わってるわけですね。II-V(ツー・ファイブ)が一つになっちゃったみたい。相対コード表記すると「IIm7/V」でしょうか。
実際にピアノではどう弾くんでしょう?
|
| 五反田: |
じゃあ、実際のボイシングを見てみよう。
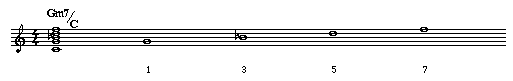
|
| ひろ子: |
あ、素直にルート(C)の上にGm7を弾いています。こういうときはテンションとか考えなくていいんですか? |
| 五反田: |
それでは構成音を詳しく見てみよう。ルートが「C」だから、「C」を1度として「Gm7」の各音を見てみると、5度、7度、9度、11度となっている。
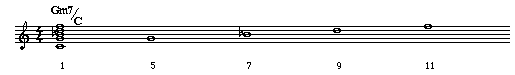
コード・ネームを「Cなんとか」と付けるとしたら、何というコードになると思う?
|
| ひろ子: |
「C79 11」のような気がするんですが、メジャーかマイナーかを決める肝心の3度が無いので決められないんですが...
|
| 五反田: |
3度が無いのが実はポイントなんじゃ。3度がないとトーナリティ(調性)が曖昧になるし、7度とのトライトーンも無いからトニックへの強い引力も生まれない。さらにルートのCと11thのFとは完全4度(厳密にはオクターブ+完全4度)の音程になり、どこかスコーンと抜けたようなサウンドになる。
|
| ひろ子: |
「青いお空にぽっかり白い雲」ってやつですね。 |
| 五反田: |
逆に考えるとこのサウンドが欲しいから、この構成音を弾いて欲しいから敢えてGm7/Cと書くようなところがあるんじゃ。例えば「C11」や「C7sus4」と書くことも出来るが、そう書かれてもどの音を鳴らしていいのかが直感的にわかりづらい。
パット見で、すぐ弾けるように「Gm7/C」と書いてあると思えばいいんじゃ。そうすると弾く方は余計なテンションとかを入れずに、素直にその指示に従うことが重要になる。
|
| ひろ子: |
テンションとかを入れてしまうとこのサウンドが得られなくなるわけですね。 |
| 五反田: |
「Gm7」をそのまま「ソ・シb・レ・ファ」と弾くかどうかはケース・バイ・ケースで、展開形を使うこともあるじゃろうが、構成音は変えてはいかんのじゃ。 |
| ひろ子: |
ポップスも難しいんですね。 |
| 五反田: |
いやいや、これはジャズでもよく使われるんじゃ。そもそもこのサウンドの起源はかのHerbie Hancock先生の「処女航海(Maiden Voyage)」だという説もある。
|
| ひろ子: |
あ、本当だ。「Am7/D」や「Cm7/F」でベタの和音を弾いています。例えば「Am7/D」では左手で「レ・ラ・レ」、右手で「ラ・ド・ミ・ソ」と弾いています。 |
| 五反田: |
この曲は「Dミクソリディアン」−「Fミクソリディアン」..と進行する曲なんじゃが、和音としては「Am7/D」-「Cm7/F」...なわけじゃ。
これ以降、ミクソリディアンではこういうボイシングをするのが一般的になった。だから、「ミクソリディアン」としか譜面に書いてない時は「IIm7/V」と弾いてみるといい。結構、ハマるぞ。
もしくは「X7sus4」とか「X11」と書いてあったり、7thコードが長く続いたりしている場合には「IIm7/V」に置き換えて弾いてみるのもいいじゃろう。
|
| ひろ子: |
今のはメジャー(長調)の例でしたが、マイナー(短調)の例はありますか? |
| 五反田: |
そうじゃな、「IIm7/V」ほど有名じゃないが、こういう曲がある。
本来、「E7→Am」となるところを「Em7→Am」としている。
|
| ひろ子: |
4段目、曲の終わりのところですね。そもそもドミナント・モーションとは「V7→I」というコード進行のことですから、「Vm7→I」ではドミナント・モーションとは言えないんじゃないでしょうか。 |
| 五反田: |
まあ、正確にはそうかもしれんが、もっと幅広く「解決」と考えれば些細なことじゃ。それより「V7→I」で発生する強い引力、言い換えれば7th臭さを「Vm7→I」で消していることがポイントじゃ。 |
| ひろ子: |
ベースは「5度→1度」という進行(5度下行、もしくは4度上行)をしているので、7thコードの三全音(トライトーン)の力を借りなくても解決できると考えればいいのかな。 |
| 五反田: |
もう一つマイナーの例を紹介しよう。通常、マイナーコードに進行するツー・ファイブは「IIm7-5→V7」にするが、これを「IIm7→V7」とするとちょっとサウンドが変わってくる。
「Am7-5」を「Am7」にすることでGマイナー(ト短調)の音階には存在しない「ミ」が登場する。
これによってサウンドのガラっと色彩が変わるんじゃ。
|
| ひろ子: |
ちょっと聴き比べてみましょう。
フラッテッド5thにすると、笑っちゃうくらいダサダサです(^_^;)。
|
| 五反田: |
これをもう少し発展させて、Dのドミナント・ペダル上でCのトライアッド(ド・ミ・ソ)にするパターンもよく使われる。
|
| ひろ子: |
いろんな方法があるんですね。つまりは「解決」の時に如何にして「7th臭さ」を消すか、がポイントなんですね。 |
| 五反田: |
初めはトライトーンの強烈な引力を使ってドミナント・モーションしていた。そのうちにトライトーンの強烈な7th臭さがダサダサに感じられ、また刺激が欲しくなってオルタード・テンションでトライトーンを包み隠すようになった。さらにはトライトーンさえ使わず、コンディミやら半音上やら、いろいろな手で「緊張→安定」を作り出して「解決」するようになった。
これはまさに音楽のそしてジャズの進化の過程なのじゃ。「如何にかっこよく解決するか」を追い求めてジャズは進化してきたと言っても過言ではない。
ドミナント・モーションの進化はジャズの進化そのものなのじゃ。
|
| ひろ子: |
観念的ですが、なんとなくわかります。「コンディミやら半音上やら」の具体例をもう少し教えてください。 |
| 五反田: |
よし。ひろ子くんは「ウラ・コード」というのを聞いたことがあるかね? |
| ひろ子: |
「ウラ・コード」ですか? |
| 五反田: |
第3部第3話のよく使われるノン・ダイアトニック・コードで紹介したbII7(フラット2度7th)のこと。通常、「Dm7 - G7 - Cmaj7」とするところを「Dm7 - Db7 - Cmaj7」にするんじゃ。
|
| ひろ子: |
理論書などを読むとG7もDb7も「ファーシ」という三全音(トライトーン)を持っている、だからDb7はG7の代理コードになる、みたいに説明しています。 |
| 五反田: |
それでもいいし、ルートが「レ→レb→ド」と半音下降すると考えてもいい。解決しようとするコードの半音上の7th、それをドミナント・コードの「ウラ・コード」というのじゃ。 |
| ひろ子: |
なぜ、「ウラ・コード」と言うのでしょう? |
| 五反田: |
フフフッ...それを言いたかったのじゃ。第3部第1話に登場した5度圏(4度圏)を覚えておるじゃろう? |
| ひろ子: |
これですね。
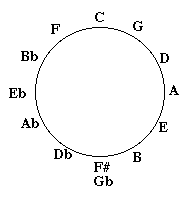
|
| 五反田: |
これでG7とその「ウラ・コード」であるDb7の位置関係を見ると円の中心に対して、真裏にあることがわかる。
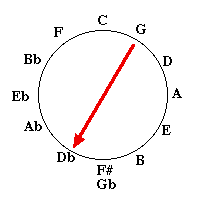
これが「ウラ・コード」の由来じゃ。
|
| ひろ子: |
へぇ〜、そうだったんだ!
でも、「ウラ・コード」そのものはドミナント・コードのテンションを含んだ和音と考えれば、取り立てて目新しいアプローチとは思えないですが...
|
| 五反田: |
そうじゃね、例えば「Db7」であれば「G7」のb9(フラット9th)と#11(シャープ11th)を含んでいる。それだけであれば今まで説明してきたことで十分かもしれん。でも「ウラ・コード」という場合はこれをツー・ファイブにして、よりアウトなサウンドを作ることを指すことが多いんじゃ。 |
| ひろ子: |
つまり、例えば「Db7」なら「Abm7 - Db7」に分解するということですね。そうすると一時的にGb(変ト長調)に転調したような響きになりませんか? |
| 五反田: |
それがポイントなんじゃよ。一時的に異なるトーナリティ(調性)を感じさせて緊張感を増す、これこそ「解決」の極意じゃないか。
例えば「All The Things You Are」や「枯葉」といった、ひろ子くんもよく知ってる曲にウラコードのII-Vを適用するのはもはや定番と言ってもいいくらい、よく使われる。
|
| ひろ子: |
「All The Things You Are」だったらこんな感じですね。
|
| 五反田: |
「枯葉」であればこうなる。
|
| ひろ子: |
トニックの解決するドミナント7thをウラコードのII-V(ツー・ファイブ)に変えているんですね。ウラ・コードを使うときはこんな風に最初からコード進行を変えて演奏するものなんですか? |
| 五反田: |
ケース・バイ・ケースじゃな。あらかじめ「ここはウラ・コードでやろう」と打ち合わせることもあるし、一般的にはソロイストが自分の判断でその場その場でウラ・コードを使う。 |
| ひろ子: |
アドリブの例で教えてください。 |
| 五反田: |
それじゃあ、またFのブルースでウラ・コードの例を見ていこう。 |
| ひろ子: |
これまで、ブルースの注目点ということで第1部第4話では8小節目、第3部第4話では4小節目と5〜6小節目について説明していただきました。 |
| 五反田: |
「ウラ・コード」は特別、何小節目という訳ではなく、ドミナント7thのところなら、どころでも使える。このソロを見てみよう。
(説明の都合上、キーをFに移調)
|
| ひろ子: |
4小節目の「Cm7 - F7」をウラ・コードのII-V(ツー・ファイブ)である「F#m7 - B7」で弾いていますね。本当に一時的にキーがE(ホ長調)に転調したかのようなアウト感があります。 |
| 五反田: |
もうひとつ、同じく3〜4小節目を「ウラ・コード」にしたアドリブを紹介しよう。
|
| ひろ子: |
二つのブルース、両方とも9〜10小節目がII-V(ツー・ファイブ)じゃないんですね。8小節目にVI7が使えない...
(;>_<;)
|
| 五反田: |
これはコルトレーンがよく使った、コードの単純化の例じゃ。「ジャズ的」なブルース進行を嫌って、わざとこうしておる。 |
| ひろ子: |
それにしてもウラ・コードの例が4小節目ばっかりですね。9小節目の「Gm7 - C7」とかの例も紹介してください。 |
| 五反田: |
これでどうだ。ウラ・コードの「C#m7-F#7」をII-Vに見立てて、III - V - II - Vになるように「Ebm7-Ab7 - C#m7-F#7」としておるぞ。
(説明の都合上、キーをFに移調)
|
| ひろ子: |
この辺になってくるとちょっと相当猛烈にアグレッシブですね。 |
| 五反田: |
「ウラ・コード」に関連して、もうひとつ、おもしろいコードを紹介しておこう。この曲じゃ。
|
| ひろ子: |
サビでサブ・ドミナントである「Cmaj7」に行く前の「C#79#11」のことですね。半音上の7thからメジャー7thに進行するんですね。本来は「G7→Cmaj7」という進行を「C#7→Cmaj7」にしていて、「G7」のウラ・コードが「C#7」です。
でも、博士、ウラ・コードでテンションをオルタードさせるとまともになってしまいません?
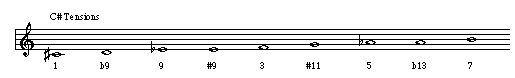
「C#7」の#11は「ソ」なので、「G7」のルートですよ!
|
| 五反田: |
その通りじゃ。「ウラ・コード」は「オモテ・コード」のテンションを含んでいるので、「ウラ・コード」のテンションをオルタードしてしまうと「オモテ・コード」のコード・トーンやナチュラル・テンションになってしまう。 |
| ひろ子: |
それじゃあ、せっかく「ウラ・コード」を使ったのに意味がなくありませんか? |
| 五反田: |
全くひろ子くんの言う通り。でもさっき見たように「ウラ・コード」のサウンドはかなり強烈じゃろう。その強烈さを緩和してさりげなくアウトのニュアンスを出すにはそのほうがいい場合もあるんじゃ。
例えばさっきの曲でもほんの1拍、歌詞でいえば「といきで〜」の「で〜」のところでさらっと使っておるが、そのちょっとした瞬間のテイストが心地いいのじゃ。
|
| ひろ子: |
ボイシングとしてはこんな風にしているんですね。
結構シンプルです。G7で考えてみると下から「#11・3・b13・1」というボイシングです。
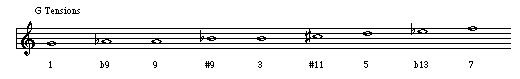
|
| 五反田: |
こういうポイントとなるコードはよけいな音を弾かずにシンプルにするのがポイントじゃ。ズージャの人はついつい考えすぎていろんな音を弾いてしまい、肝心のサウンドを濁らせてしまうことがあるので、気を付けることじゃ。 |
| ひろ子: |
はい、わかりました。それにしてもこのコードって一般的なんですか? |
| 五反田: |
「Dm7/G」ほどではないが、かなり普及しておる。例えばジノ・バネリの「I Just Wanna Stop」のサビ前でも使われておる。
そのほかにもSwing Out Sistersの「Break Out」のサビ前、「Feel Like Makin' Love」のサビ前などじゃ。
|
| ひろ子: |
サビがサブ・ドミナントから始まる曲でその直前に使うパターンばかりですね。それにしてもポップス系ばかりです。 |
| 五反田: |
マイク・マイニエリの「I'm Sorry」でも使われておる。
|
| ひろ子: |
それじゃあ、「I'm Sorry」を紹介すればいいのに。あえてポップス系の曲を選んだのには何か、理由でもあるんですか? |
| 五反田: |
ジャズばっかり聴くことがジャズの勉強ではないということじゃ。学ぶ素材は身近なところにもいっぱいある、ということを言いたかったのじゃ。 |
| ひろ子: |
なるほど、含蓄のあるお言葉です。
とか何とか言って、博士、実は南野陽子さんが好きっだったりして...
|
| 五反田: |
(^_^;).....
|
| ひろ子: |
・・・・(絶句)
今回のマイナス・ワンはハンコックの処女航海にしま〜す。
|
| 次回はジャズ最大の難曲、Giant Stepsを分析します。 |
| つづく |