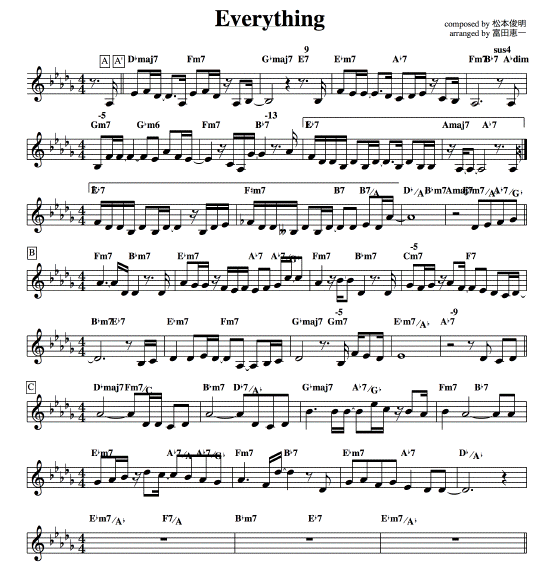
| 目次 | 前話 | 次話 |
 |
||
二話目はMisiaの2000年10月リリースのバラード「Everything」。
個人的な好みからすればMisiaであれば、「陽の当たる場所」や「Believe」みたいなゆったり目の16ビートで、大きなノリで唄うような曲の方が好きなのじゃが、プロモーション・ビデオに出てた少女が可愛かったので、これにしました。
(「ズージャでGO!」だったらこの辺でひろ子くんのつっこみが入るところじゃが)
まあ、もちろんそれだけが理由じゃないことはこのページをご覧の方々には自明なことだと思うが...(って、やっぱりそれも理由の一つだったのか!)
まあ、とにかくさっそく、始めよう。(ほら、シャレじゃないでしょ)
右の譜面はイントロを省略して、1コーラス目とそれに続く間奏までを載せている。
MIDIの方は1コーラス目+2コーラス目まで作ってある。
オリジナルの構成はA−A’−B−C−間奏−A’−B−C’−C−間奏−C’−C。Cがいわゆるサビというやつじゃ。
この曲の第一の、そして最大のポイントは「バラードであること」。
「またまた、当たり前のことを!」と言うなかれ。「バラードである」ということはテンポが遅いということじゃ。テンポが遅いとどうしても間が多くなる。間が多くなって緊張感が薄れてしまうといけないので、適度に間を埋める必要が出てくる。メロディラインで間を埋めてちゃ、バラードにならない(音楽にならない?)ので、バックのアレンジで間を埋めることになる。
そのアレンジで間を埋めるときによく使用される技法が「飾りコード」というやつじゃ。「飾りコード」というのは例によってわしの造語じゃが、曲の骨格には影響しない、あえて言えばそのコードがなくても曲としては成立しうるコードのことじゃ。
右の譜面で赤丸で囲んだコードがそれじゃ。結構、いっぱいあるじゃろう。そしてこうした「飾りコード」の中に「ツボ」が詰まっておるのじゃ。
最初の「飾りコード」は早くも2小節目に出てくるE79じゃ。
次のEbm7に進行するための半音上の7th、いわゆる「ウラコード」。基本といえば基本じゃが、IIm7(2度マイナー7th)での使用例はそんなに多くない。「ズージャでGO!第3部第6話」で説明した「ウラコード」はIVmaj7(4度メジャー7th)に解決したが、これはその応用と言えるかもしれん。IIm7はIVmaj7の代理コードでもあるからのう。
ここでわざわざE79とナチュラル9thのソbを加えてあるのはポイントじゃ。「ウラコード」は元のキーに対し遠いコードなので、どうしてもサウンドが過激になる。それを緩和するために次のコードにも含まれるソbを加えていると考えられる。
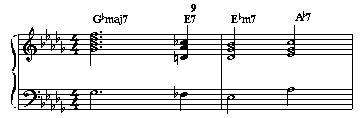
ソbは次のコードの3度でもあるから、それだけ和音の流れもスムーズになるし、アウト感も薄められるというわけ。この辺の考え方はIVmaj7(4度メジャー7th)の時と同じじゃな。
訳あって一つ飛ばして3つ目の「飾りコード」のAmaj7。
これも次のAb7に解決する「ウラコード」とも言えるんじゃが、さっきのE79とはちょっとニュアンスが違うのが分かるじゃろうか。さっきのE79は流れをスムーズにするためのさりげないウラコードだったが、こちらは眠気を覚ますような刺激がある。「ウラコード」と言うより、単に半音上と理解した方が正解かもしれない。
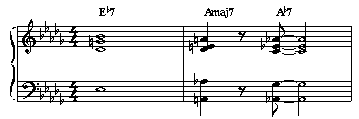
Bへ移る直前のA’の最後のAmaj7はさっきと同じで、「寝た子を起こす」半音上じゃが、それだけではない理由は後述。
Bの7小節目、サビにいく前のGm7-5は「サブドミナントの半音上のハーフ・ディミニッシュだから、魅惑のハーフ・ディミニッシュだわ!」と思った方、よく勉強してらっしゃるが、もう一歩じゃ。これはGbとAbの仲を取り持つコードととらえた方がいい。
「ズージャでGO!第3部第2話」で説明した「パッシング・ディミニッシュ」に近い。コードのルート、つまりベースが「Gb→G→Ab」と半音づつ上がってコードの流れをスムーズにする、という技法じゃ。Gdimだと「ミ」が入っててアウト感があるが、Gm7-5だと穏やかになるじゃろう。これぞディミニッシュに似てる「ハーフ・ディミニッシュ」ならではとも言えよう。
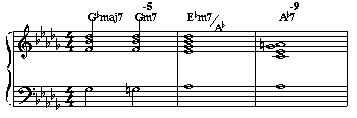
「飾りコード」に続く、間を埋める技その2は「飾りベースライン」。「飾りコード」が和音で間を埋めるのに対し、「飾りベースライン」はベースだけで間を埋めると言うこと。基本的な考え方は「飾りコード」と同じじゃ。「飾りコード」と「飾りベースライン」はどちらか一方、しばしば両方を駆使して間を埋めていく。
さっき、訳あって飛ばしたAの4小節目のAbdimなんかが「飾りコード」と「飾りベースライン」合わせ技の例じゃ。
Abdimと書いたが、正確にはBb7-9/Abと書くべきだったかな。実はAbdimとBb7-9は下の図で見ても分かるように構成音が殆ど一緒なんじゃ。
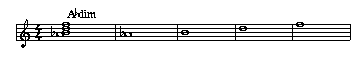
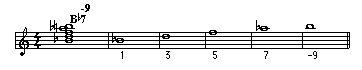
「半音上のディミニッシュはフラット9th」と覚えるといい。でもポイントはそれじゃなくて、ベースがBb→Abとダイアトニックに下降することが重要。5小節目への橋渡しと弾みをつける役目がこのAbにあるんじゃ。これがあるとないとでは大違い。
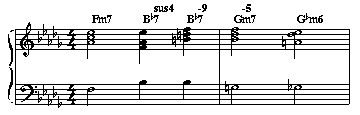
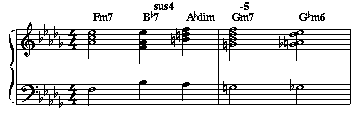
5小節目から「コール・ポーターのハーフ・ディミニッシュ」で始まる、印象的なメロディが流れるわけだが、Gm7-5への流れをスムーズにして、よりGm7-5を際だたせておる。この5小節目から2小節がわしは大好きなんじゃ。
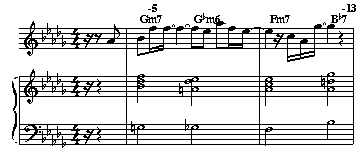
この「ベースだけ下降」パターンはその後も何回も出てきて、A’の8〜9小節目もそのバリエーションじゃ。コードとしてはF#m7→B7→Dbなんじゃが、ベースが下図のように下降してスムーズな流れにしている。
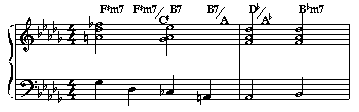
9小節目はDb/Abになったので結果的にドミナントペダルっぽくなっている。
続く10小節目も同じくベースが下降するパターンじゃが、ちょっとおもしろい。よくあるのはBの2小節目にも出てくる、ドミナント7thコードのルートが下降するやつだ。
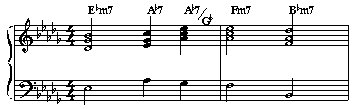
II-V-III-VII、この場合だとEbm7−Ab7ーFm7ーBbm7と進行するときにVのルート、Vのルートの全音下と続けることによってIIIへの進行がスムーズになる。この手はかなり一般的なんじゃが、ここではこんな風にやっている。
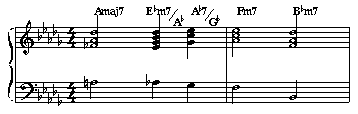
Ebm7/Abはドミナント臭さを避けるために使われるコード(ズージャでGO!第3部第6話)じゃが、これの応用と言えるかな。その前に飾りコードのAmaj7があるので、ベースラインとしては9小節の2拍目から「シb−ラ−ラb−ソb」と綺麗に下降することとなった。
しかし、「飾りのベースライン」の決定版と言えるのはなんと言ってもCの1〜2小節じゃろう。右の譜面では
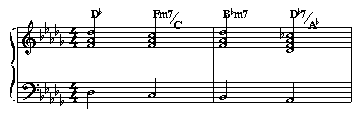
としたんじゃが、
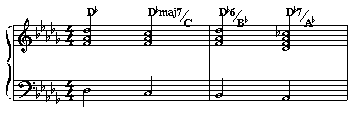
と書いた方がわかりやすかったかも。Fm7やBbm7はDbの代理コード(構成音がほぼ一緒)なわけで、元をただせばコード進行はこんなにシンプル。
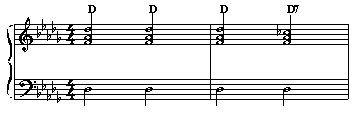
サウンドも随分と貧弱だが、これに下降するベースを加えるとあら不思議。
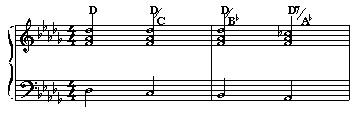
なんとゴージャスになってしまうことやら。このベースの下降はトニックからサブドミナントへ進行するときの定番とも言える。
ジャズなんかではII-Vを使って、こうしちゃうことの方が多い。
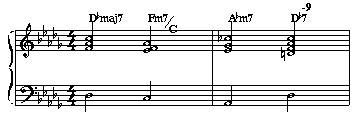
これはこれでかっこいいけど、違う曲になってしまう気もするよね。
「飾りベース」とは言い難いが、触れておかねばならないのが間奏のF7/A。AbのペダルからBbm7へのつなぎにもなっている。
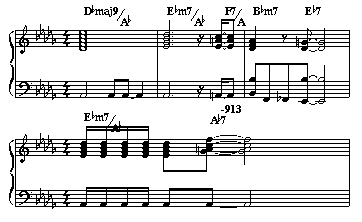
実はこの3度をルートにしたドミナントはよく使われるんじゃ。上にのせるコードは7thでなくても構わない。トライトーンがなくてもベースがA→Bbと半音上昇するだけで解決させてしまおう、という技じゃ。
次の例は3度ルートドミナント→トニックの3連発じゃ。どこかクラシックな響きもある。
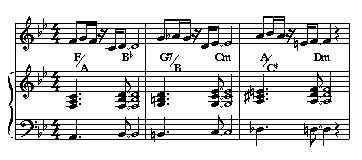
これが言いたかったので間奏まで譜面を載せたわけなんじゃが....
こうした「飾りコード」や「飾りベースライン」はどこまでが作曲者の意図でどこからが編曲者のアイディアなのかは微妙なところ。そんな意味もあって編曲者の名前も譜面に載せました。個人的にはピアニストがピアノを弾きながら作曲すると「飾りベースライン」までは作ってしまうことが多いように思うのだが、いかがだろうか?
ん〜ん、重要なポイントじゃないかもしれないけれど、わしがこの曲を取り上げた理由の一つでもあるのが、このポイント。
バラードだし、後半は半音上に転調でもして、さびを繰り返して終わるんだろうなと思っていたら、案の定半音上に転調してサビが始まったんじゃが、。C’−Cと来たところでわしは思わず唸ってしまった。
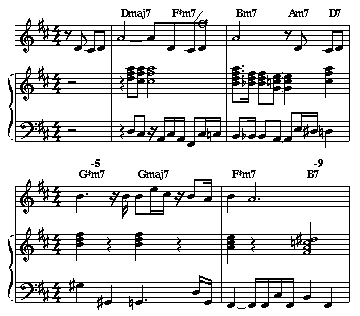
賢明な方は分かったと思うが、3小節目をGbmaj7→Ab7からGm7-5→Gbmaj7に変えていたんじゃ。(ここでは半音上がってG#m7-5→Gmaj7)。II-Vを魅惑のハーフ・ディミニッシュに置き換える技はKinki−Kidsの曲で説明したよね(ズージャでGO!第3部第8話)。そのパターンなんじゃが、メロディ・ラインは同じだがコードだけをさりげなく変えてみる、という心憎い演出じゃ。おそらくは大半の人は気にもとめない、でも気づいた人は「ニヤリ」としてしまうもんじゃ。「お主もなかなかやるのう」とででもいったところか。
2コーラス目以降に登場するC’じゃが、譜面にするとこんな感じじゃ。
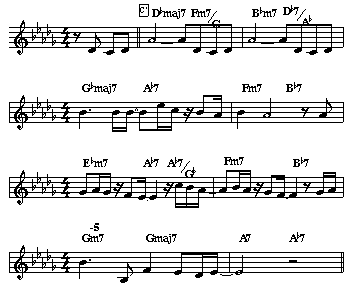
ここでもGm7-5が出てくる。もしかしてラストの伏線?
バラードということで白玉ストリングスも多用されているが、押さえておきたいのはCの4小節目。
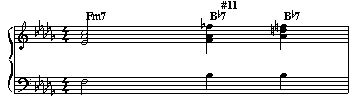
Bb7のファにいく前に半音下のミで引き留めるようなニュアンスを出している。テンションとしては#11(シャープ11th)なんじゃが、経過音と考えるのが正しい。映画音楽あたりでよく使われる技法じゃ。
と言うわけで、今回は随分とディテールに拘った話になっちゃったけど、いかがだったろうか。改めて「Everything」を、そしてMisiaさんを聞いてみて欲しい。あと、ビデオ・クリップも見て欲しいな〜。本当に女の子が可愛いんだから。(って、結局最後はそれかよ!)
アルバム「Marvelous」BVCS-21022
オフィシャル・ページ http://www.rhythmedia.co.jp/misia/