| 前回、五反田博士に「致命的な欠点がある」と言われたひろ子、果たしてその致命的な欠点とは? |
| ひろ子: |
博士! この前、言ってた私の致命的な欠点って何ですか? あれ以来、気になって眠れなくって。 |
| 五反田: |
そんなに気に病むことではないんじゃ。ベースの関くんなんか、未だによくわかってないんだから。
それじゃあ、ひろ子くん。もう一度、Fのブルースを弾いてみたまえ。
|
| ひろ子: |
このあいだ、楽譜を買ったらFのブルースのソロが載ってたんですけど、それを弾いてもいいですか? |
| 五反田: |
まあ、いいじゃろう。弾いてみなさい。 |
| ひろ子: |
|
| 五反田: |
今度はわしが同じことをやってみよう。印象を近づけるためにピアノで弾いてみるぞ。
違いがわかるかね?
|
| ひろ子: |
私の方が軽いというか、ちゃかちゃかしてるというか...
とても同じメロディを弾いてるようには聞こえませんでした。
|
| 五反田: |
それが「ノリ」とか「スウィング感」なんて呼ばれるものの違いなんじゃよ。
スウィング感はその時代時代によって変わって行ったり、ひとりひとり異なっていたりする。
初めて聞いたアルバムでも「あ!、これはジャッキー・マクリーンだ。」とわかっちゃったりするのも、大半はこのスウィング感の違いに依ったりする。そういう意味では演奏者の「個性」の大きな要素であるわけだ。
|
| ひろ子: |
じゃあ、この「ちゃかついた」感じが私の個性なわけですか? |
| 五反田: |
現時点でのひろ子くんの個性であることは間違いな。ただ、個性とひとことで片づけてしまうと教えようがないが、やはり、基本というのはある。
ひろ子くんの8分音符は「タッカ、タッカ」と聞こえるんじゃが、のう。
|
| ひろ子: |
本で読んだんですが、4ビートで8分音符を弾くときは を を のように弾きなさいとあったんで。 のように弾きなさいとあったんで。 |
| 五反田: |
それはそれで間違いじゃないんじゃが、ひろ子くんが のように「弾かなきゃいけない」と思いこんだ瞬間、間違いになるんじゃ。 のように「弾かなきゃいけない」と思いこんだ瞬間、間違いになるんじゃ。
8分音符のオモテとウラの長さがあまりにも違いすぎるんじゃ。
もっとオモテとウラの長さを揃えるというのか、ウラを弾くタイミングをもっと前にするというか、つまりはもっと普通の8分音符に近く弾かなければいけない。
演奏の心得としては
「4ビートで8分音符を弾くときは、なるべく均等に「ターター、ターター」と弾く様なつもりで弾くと、ちょうどいい具合に「ターカ、ターカ」と弾ける。決して「ターカ、ターカ」と弾こうとしないこと!」
と肝に銘じておくがいい。
|
| ひろ子: |
意識して「タッカ、タッカ」と弾くんじゃなくって、あくまで均等に弾こうとした結果、「タッカ、タッカ」であるということですね! |
| 五反田: |
あと、その本には「ウラにアクセントをつけなさい」みたいなことは書いてなかったかね? |
| ひろ子: |
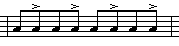 ってことですよね。それも書いてありました。 ってことですよね。それも書いてありました。 |
| 五反田: |
これもちょっと言葉が足りなくて、
「オモテにアクセントを付けるのはごく自然のことだけど、そればっかりじゃつまらないので、オモテと同じぐらいの頻度で、ウラにもアクセントをつけなさい」というのが、正しい表現なんじゃよ。
ウラにアクセントを付ける習慣がない人に、「ウラにもアクセントを付けなさい」と強調しすぎて、こういう表現になったわけじゃ。
|
| ひろ子: |
「アクセントは常にウラじゃなきゃいけない」わけじゃ、ないんですね。 |
| 五反田: |
そうじゃ。また、アクセントというのはフレーズや音の高低、前後の音との関係などに左右されるんじゃ。例えばこんな単純なちょっとダサダサなフレーズを弾くとする。
このフレーズではウラにアクセントを付けるのは不可能なんじゃ。無理にウラにアクセントを付けると音楽的に変なことになっちゃう。で、ちょっとフレーズを変えてみると
|
| ひろ子: |
アクセントが半拍ズレて、ウラに入りましたね。 |
| 五反田: |
そうじゃ、フレーズをちょっと変えて、半拍ズレたウラを高い音にした結果、今度は「ここにアクセントを入れないとおかしい」位に自然とウラにアクセントが付いたな。つまり、アクセントとフレーズは一体であって、アクセントだけウラに付けるなんてことは不可能なんじゃ。さらにこうするとオモテのアクセントも格好よくなる。
8分音符ではオモテじゃが、4分音符のウラである、2拍目にもアクセントが付いたな。これはいったん下がった音を再び上に上げたことによって生まれたんじゃ。こんな風にオモテもウラも自由自在に「操る」ことでメロディに起伏ができて、音楽が生き生きしてくるんじゃ。
まあ、実践的にはこんな風なフレーズなら使えるようになるかな? いわゆる「こぶし」を回すような感じじゃな。
|
| ひろ子: |
ほんのちょっとで印象が全然、変わるんですね。もっともっと勉強しなくっちゃ! |
| 五反田: |
ところが、ひろ子くんの致命的な欠点はここからなんじゃよ。以前、教えた「ベースラインをピアノで弾く」をもう一度、やってみてくれないか?
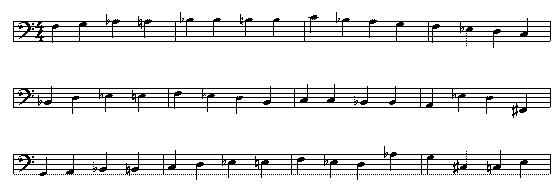
|
| ひろ子: |
はい。
|
| 五反田: |
じゃあ、同じようにわしも弾いてみるぞ。
|
| ひろ子: |
あ、何か違う! |
| 五反田: |
違いがわかりやすいようにパソコンのシーケンサー・ソフトの画面で見比べてみよう。
| ひろ子の弾いたベース・ライン |
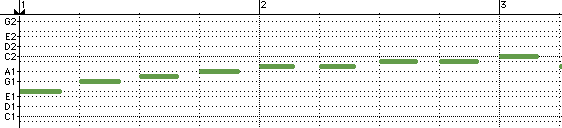 |
|
| 博士が弾いたベース・ライン |
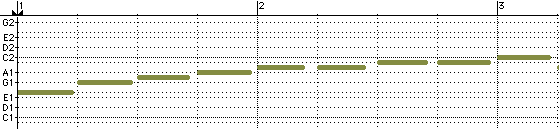 |
どうじゃ、違いが解るかね?
|
| ひろ子: |
私の弾いた方が棒が圧倒的に短いですう。 |
| 五反田: |
弾いた音の長さが棒の長さになっておるんじゃ。つまり、わしは4分音符の90%ぐらいを弾いているが、君は4分音符の60%ぐらいしか音を弾いていないことになる。
楽譜にするとどちらも
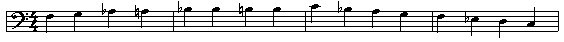
じゃが、君が弾いてるのは
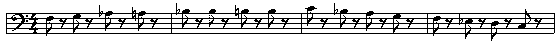
のように弾いていることになる。この音符の長さがわしと君との決定的な違いであり、ひろ子くんがスウィング出来ない最大の原因でもあるんじゃ。
全ての音楽、全ての楽器において音符を長く弾くのは基本中の基本なのじゃ。
|
| ひろ子: |
確かにさっきのベースラインで見ると一目(一聴?)瞭然でしたね。 |
| 五反田: |
4ビートに於いてベースのRunningはスウィング感の全てなんじゃ。これなしには4ビートのスウィング感は成立しないし、逆に言えばベース以外は「飾り」に過ぎないとも言える。
曲のニュアンスを把握させると同時に、4ビートのスウィング感も身につけてもらおうと思って、ああいう練習をさせたんじゃよ。
|
| ひろ子: |
博士!、そこまで考えていてくれたんですか? ひろ子、感激!...
で、「音符を長く弾く」のは4分音符だけでなく、8分音符や16分音符でも同じなんですね。
|
| 五反田: |
その通りじゃ。さっきからひろ子ちゃんは「タッカ、タッカ」と言っておったが、「ターカ、ターカ」が正しいんじゃ。いや、むしろ「ダーダー、ダーダー」と言った方がいいかもしれん。
しかし、この「音符を長く弾く」というのは、言うは易し、やるのは大変なんじゃ。前の音を出来る限り伸ばしておいて、素早く次の音に移るわけじゃからな。
でも、これが出来なければいつまでたってもスウィングしないのだよ!
|
| ひろ子: |
わかりました、何とか頑張ってみます。でも、こういう事って昔、エレクトーンを習ってた時にも教わったこと、ありませんでした。 |
| 五反田: |
これこそ、「五反田流 音楽の奥義」なんじゃよ。 |
| ひろ子: |
それにしても博士はどこでこういったことを勉強したんですか? 学校や先生に習ったことはないとおっしゃってましたよね。 |
| 五反田: |
別に教わらなくても勉強は出来るのじゃよ。じゃあ、次回はその辺の話をするとしよう。
さあ、ひろ子くんはもう一度、ブルースのベースラインを「音を伸ばして」弾く練習じゃ。
|
| つづく |