| ブルーノート・スケールを教わって、ブルースのアドリブに挑戦したひろ子だったが、曲の流れが掴めなくて、上手くできない。 五反田博士はベース・ラインを自分の楽器で弾くことで曲の流れを体に染み込ませる練習をさせた。 |
| ひろ子: |
博士!、ベース・ラインを弾くと、本当にコードの流れが掴めますね。 |
| 五反田: |
そうじゃろう! もっと慣れてきたら自分でベース・ラインを作ってみるといい。必ずアドリブ練習に役立つぞ。
さあ、それじゃあ、前回もやった「Fのブルースをブルーノートだけでアドリブする」にもう一度挑戦してみよう。
|
| ひろ子: |
今回もコードは無視しちゃうんですか? ちょっと勉強してきたんですけど... |
| 五反田: |
細かいことは気にせず、ベース・ラインを弾いて掴んだ、曲の流れを大事にして弾いてみるんじゃ。 |
| ひろ子: |
|
| 五反田: |
いくつか、一般的なアドバイスしてみようか。
まず、何となく気づいてはいるじゃろうが、アドリブを弾くときは8分音符を主体に弾くのが基本じゃ。
これは決して8分音符以外を使っちゃいかんと言ってるのではないぞ。8分音符を主体に、3連譜・16分音符や2分音符・4分音符などももちろん使うが、フレーズの大半は8分音符で弾くということじゃ。
|
| ひろ子: |
私も無意識に8分音符で弾いていたみたいです。 |
| 五反田: |
そうじゃったな、その点は合格じゃ。
次に、最初からバリバリと弾くのはあまりよくない。最初は音符を少な目にして、自分が演奏したいメロディが見えてきてから、徐々に音数を増やしていくのが基本じゃ。
つまり、アイディアも湧かないのに意味のない音を無闇に鳴らしちゃ、だめっていうこと。
|
| ひろ子: |
アイディアが湧かないときは、いつまでも弾いてはいけないんですか? |
| 五反田: |
そういう時は、ひとつのモチーフやフレーズ、例えばテーマのメロディを引用して、それを少しづつ変えていって、フレーズのアイディアを導いていく、なんていう手が結構、使えるぞ。
|
| ひろ子: |
テーマを引用したら、ずーっと引用しっぱなしになっちゃったりして。 |
| 五反田: |
初めはそれでもいいかもしれんのお。テーマのメロディが一番、その曲の良さを表している場合も多いから、テーマのメロディを何回も弾いてみるのはいい練習になるかもしれんよ。
次は、「長いフレーズを弾くことを心がける」ことじゃ。
この「長い」というのは、例えばコードとコードにまたがるような長さ、あるいは4小節区切りをまたがるような長さということ。一つのコードに対して一つのフレーズなんていうアドリブは最悪なんじゃ。
また、大体の音楽は4小節で何となく区切られている。その区切りをまたがったメロディを弾くと、曲の基本的流れとは別の流れが出来て、曲の奥行きが広がるものじゃ。
いずれにしても「ブチ切れフレーズ」はいかんということじゃ。かといって、「32小節、休符なし」なんてのはいかんぞ。これは目安じゃが、自分の呼吸する間隔でフレーズを区切るのがいいようじゃ。
|
| ひろ子: |
呼吸する間隔って、管楽器だけの話じゃなくてですか? |
| 五反田: |
そうじゃ。何しろ音楽を聞いてるのは呼吸している人間じゃからな。その生理的リズムに反するような演奏は管楽器に限らず、あまり受け入れられないもんじゃよ。
逆に意識的に呼吸よりちょっと長めのフレーズを弾くと、聞いている方も呼吸が止まり緊張感が増すのじゃ。
|
| ひろ子: |
管楽器だと今のようなフレーズは大変じゃないんですか? |
| 五反田: |
大変だからより一層、緊張感が出るのじゃよ。
今度はもうちょっと細かいことも言うと、フレーズは小節の「ドあたま」から始めないこと。「ドあたま」とは1拍目のオモテということ。下の3つを比べてみるとわかるじゃろう。
このようにちょっと前やちょっと後にフレーズを始めるだけも雰囲気はかなり違うものじゃ。
|
| ひろ子: |
そういえば私のアドリブは「ドあたま」から始まってましたね。ちょっとダサダサ。 |
| 五反田: |
もひとつ細かいことで、ジャズのブルースでは実は8小節目がキモなんじゃ。 |
| ひろ子: |
わたしもそう思ったんですよ、ここが何となくかっこいいと。 |
| 五反田: |
このD7というサウンドはブルースに限らずジャズのいろんな曲に登場する。
ジャズばかりじゃない、君もよく知ってる「夏が来ーれば思い出す〜」でも、最後の「静かな尾瀬〜」とママさんコーラスならわざとらしくフェルマータするところが同じサウンドじゃ。
このD7をいかにおいしく料理するかがジャズマンの腕の見せ所となるわけじゃ。
|
| ひろ子: |
それはD7だからなんですか。他のコードじゃだめなんですか? |
| 五反田: |
あくまでキーがFの時のD7だからということじゃ。キーがCならA7、キーがEbならC7でも同じサウンドじゃ。 |
| ひろ子: |
すいません、よくわかりませんが... |
| 五反田: |
まあ、今日のところはキーがFの時のD7だけを覚えておこう。ここでこんなフレーズを弾くと、単純なブルースも幅が広がるじゃろう。ファ#とミbを使うのがツボじゃ。
|
| ひろ子: |
ここはブルーノートを使っちゃだめなんですか? |
| 五反田: |
だめというわけではないんだ。こういうフレーズを加えるとよりサウンドのカラーが豊かになるということじゃよ。
まあ、このへんで以上のことを踏まえた演奏を聴いてみようか。「Hot Struttin'」という、ミディアム・スローのFブルースじゃ。練習するならこのくらいの遅いテンポから始めなさい。
もうひとつ、アドリブの構成ということについて説明しておこう。次のようなグラフを考えてみよう。
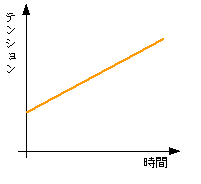
これをわしは「盛り上がり曲線」と呼んでおる。横軸はアドリブを開始してから終了するまでの時間を表し、縦軸は演奏のテンション、そう、盛り上がり具合とでもいうか、そういうものを指していると考えてくれたまえ。
音楽に限らず、映画や小説でも「だんだん盛り上がる」のが普通じゃろう。アドリブでも同じなのじゃよ。だんだんに盛り上がってきて、最後にクライマックスに達するようにアドリブする必要がある。これが逆になってみい。尻つぼみというか、息切れしちゃったみたいな、情けないことになっちゃうじゃろう。
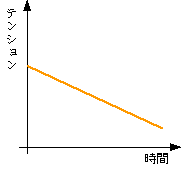
|
| ひろ子: |
私のアドリブは全然、盛り上がらなかったですね。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ。この「盛り上げる」というのはなかなか骨の折れることで、それなりに経験とテクニックが必要じゃ。そのため特に初心者はどんなに頑張っても、そんなには盛り上がれない。つまり、テンションの最大値が熟練者より低いわけじゃ。
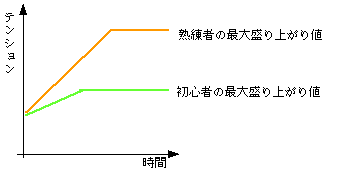
これを例えば左下の図のようにある程度、高いテンションからアドリブを始めてしまうと盛り上がりの幅が小さくなってしまう。なるべく低いテンションから始めた方がよりダイナミックな演奏ができるじゃろう。
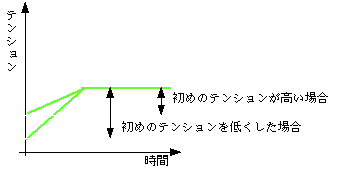
さらに音楽には「盛り上がりと音数・音程の比例の法則」というのがある。
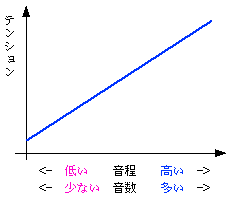
音数を増やせば増やす程、音程を高くすればするほど、盛り上がるという法則じゃ。
|
| ひろ子: |
「初めは音数を少なく」というのは、これにも当てはまるんですね。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ。まあ、曲によってどういう「盛り上がり曲線」を想定するかは全くの自由で、例えば下のような一旦、盛り下げてからまた上げるというパターンもある。
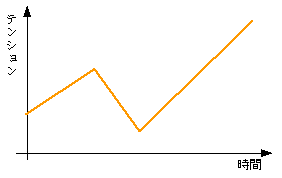
しかし、やってみるとわかるが、一旦下がったテンションをまた持ち上げるのはかなり大変じゃ。初めのうちは一直線に盛り上がるような構成にするのがいいじゃろうな。
|
| ひろ子: |
そんな構成とか、全く考えていませんでした。 |
| 五反田: |
これはなかなか気づかないことで、無意識に出来ている人もおるが、出来ていない場合が多いんじゃ。どこの本にも載っておらんじゃろう。構成を考えたとこで実践出来るかどうかは別じゃが、何にも考えてないより、頭の片隅にでも意識している方がいい演奏ができるはずじゃ。
最後にもう一度まとめておくと
- 8分音符を主体に弾く
- 初めは少ない音数で。意味のない音は弾かない
- テーマのメロディを引用してもいい
- フレーズは長めに。呼吸の間隔を目安に
- フレーズはドあたまから始めない
- キーがFの曲ではD7がキモ
- 「だんだん盛り上がる」ようなアドリブの構成を想定しながら弾く
|
| ひろ子: |
いろんなフレーズを弾けるようになるには、普段はどんな練習をすればいいんでしょうか? |
| 五反田: |
いろいろあるが、一つはソロを書いてみることじゃ。
アドリブとして瞬間的に弾くんじゃなく、じっくり少しづつメロディ・ラインを作って楽譜に書くのじゃよ。
次にその楽譜を見ながらそのメロディを暗記するまで何回も弾く。
暗記したところで、今度は譜面を見ずに弾きながら、書いたメロディをくずしたり変えたりしてみる。そんな練習が有効だと思うぞ。
|
| ひろ子: |
楽譜に書く必要はあるんですか? |
| 五反田: |
大いにあるんじゃ。その点に関しての説明は後日しようと思っておる。
まあ、いろいろ話したが、要するにアドリブは「唄ってなければいけない」ということなのじゃよ。「唄って」いれさえすれば、ブルーノート・スケールだけのアドリブでも全然構わないし、「唄って」いなければどんなに音楽的に高度なことを演奏したところで、何の価値もないのじゃ。
ところが残念ながら今のひろ子くんには、どう頑張っても「唄えない」致命的な欠点があるのじゃ!
|
| ひろ子の「致命的な欠点」とは何なのか? ひろ子に明日はあるのか? 次回をお楽しみに! |
| つづく |