| ノリの極意を教わったひろ子は、よりジャンプ・アップするためにコピーについて博士に聞いてみた。 |
| ひろ子: |
「コピーをしなさい」って、よく本に書いてあるんですが、コピーってそんなに大事なんですか? |
| 五反田: |
もちろんじゃ、今のわしがあるのもコピーのおかげと言ってもいいくらいじゃ。
レコードやCDから音を採って、それを自分で弾けるように練習するというのは、自分の演奏の持ちネタが増えるというメリットについては、言うまでもないことじゃろう。
|
| ひろ子: |
それはもちろん、そうですけど。でも、コピー譜みたいのが売ってるじゃないですか。それで十分なような気もするし、コピーって難しそうだし... |
| 五反田: |
それが大きな間違いなんじゃよ!
コピーのメリットにはもうひとつ大きな、いやむしろこっちの方が重要かもしれん、「耳を鍛える」という大事な意味があるのじゃよ。
|
| ひろ子: |
「耳を鍛える」って? |
| 五反田: |
ジャズはみんなで即興演奏するものだろう?
誰かがこう弾いたらこう反応する、みたいなインタラクティブなものでしょう?
でも「反応」するためには相手が何を意図して何を弾いたが解らなければ反応出来ないじゃない。
でも、これって実はリアル・タイムのコピーをやってることと同じでしょう!
|
| ひろ子: |
...... |
| 五反田: |
でもそんなこと、いきなり出来るわけがないじゃろうが。そのためには普段からコピーによって「耳を鍛えて」おかなくちゃ。
売ってる楽譜は確かに便利だけど、楽譜だけじゃ伝えきれない、ニュアンスとかアティキュレーションとか、前回に説明したスウィング感だって所詮、音を聞かなきゃ解らないでしょう。
結局、頼りになるのは自分の耳だけなんだよ!
|
| ひろ子: |
博士、わたくしが間違っておりました。でも、何をどうやってコピーをしたらいいのかがわからなくて... |
| 五反田: |
特に「何を」というのが、初めのうちはなかなかわからんじゃろうな。
コピーのやり方にもいろいろな種類があって、それぞれに目的と役割があるんじゃ。
大まかに次の3つに分けられるかな。
- 1曲分のソロなどを全部、コピーする
- 気に入ったフレーズをピック・アップしてコピーする
- 曲の構造やコード進行だけをコピーする
1番目は通称、「完コピ」とも呼ばれる、そっくりさんに成るぐらい、真似るコピー法じゃ。音楽は言葉と同じで、「真似る」ことが一番の上達法じゃからな。
全部をコピーすることで、ソロの構成やフレーズの繋げ方、盛り上げ方なんかを理解することが出来る。
|
| ひろ子: |
でもそれって大変じゃないですか? 時間もかかるし。 |
| 五反田: |
もちろん、大変じゃ。でもそれだけにコピーし終えたときの達成感は堪らないものがあるし、実はコピーしてる最中にそのフレーズが身についてしまってたりするもんじゃ。これは買ってきた楽譜では決して得られないぞ。
2番目はいろんな人のいろんな演奏をつまみ食いするようにコピーする方法じゃ。
|
| ひろ子: |
ギターのマイク・スターンさんもやってるって、雑誌に書いてありました。 |
| 五反田: |
これはコピーする範囲も短くて済むから、そんなに大変ではないじゃろう。コピーの練習にもなるしな。 |
| ひろ子: |
そうですね! これなら私でも出来るかもしれない。これでコピーに慣れてから「完コピ」に挑戦してみようかな。 |
| 五反田: |
ただ、そういった断片をコピーしても自分のプレイに結びつけるのはかなり難しい。マイク・スターンくんぐらいの熟練者でなければ、それを生かすことはなかなか出来ないものじゃ。 |
| ひろ子: |
そのためにはやはり、「完コピ」しなきゃだめだって言うんですか? なんか、卵と鶏みたいな話になってきましたね。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ、そこが悩ましいところじゃな。まあ、片っ端から「いいな」と思ったフレーズをコピーしてみるしかないね。そうするうちに耳も鍛えられてきて、コピーも簡単に出来るようになるし、「気に入ったフレーズ」を選ぶ力も養われてくる。 |
| ひろ子: |
具体的にどうやってコピーするんですか? |
| 五反田: |
人によってやり方はいろいろだろうけれど、わしはまず、コード進行をコピーするんじゃ。
アドリブ・フレーズをコピーしたところでそれがどういうコード進行の上で演奏されたかがわからなければ分析のしようもないし、応用も出来ないじゃろう。
|
| ひろ子: |
コードって、コピーするのは難しくはないんですか。ピアノの一音一音を聞き取るんですか? |
| 五反田: |
そういう場合もあるが、大体のサウンドでいいんじゃ、雰囲気が合っていれば。 |
| ひろ子: |
その雰囲気を合わせるのが難しいんじゃないんですか? |
| 五反田: |
ん? そうかもしれんなあ。でも基本はベースをコピーすることじゃ。ベースをコピーすればだいたいの雰囲気は掴めるものじゃ。 |
| ひろ子: |
ベーシストでもないのにベースをコピーするんですか? それにベースをコピーしただけでどうして雰囲気が掴めるんですか? |
| 五反田: |
ベースはリズムとコードの基本だからな。それにコード進行のパターンというか、ツボもあるから、だいたいのところは楽器がなくても耳だけでコピー出来るんじゃ。 |
| ひろ子: |
え? そのツボを教えて下さい! |
| 五反田: |
まあ、それはまた後日ということで。とりあえず、コード進行はわかったとしてそこから始めよう。
まず、コピーしたい素材をカセット・テープに録音する。
今はやりのMDではだめなんじゃ。
それを安い、壊れても惜しくないようなテープレコーダで再生して、少しづつ、例えば4小節とか1小節とか、場合によっては1音づつ、コピーしていく。
|
| ひろ子: |
どうしてMDじゃだめなんですか? それに安い、壊れてもいいようなテープレコーダだなんて。 |
| 五反田: |
テープを回して、楽器で音を弾いて「こうかな? 違うかな?」と試行錯誤を繰り返すわけじゃから、再生−巻き戻しを何十回もやるわけだ。
MDや、カセットでも高級な「フェザータッチ」ものや「リモコン」では素早い音出し、微妙な巻き戻しが難しい。
やはり昔ながらの「ゴリッと押し込む」ような機械的なボタンの方が使いやすいのじゃよ。
しかし、これをやると大抵の機械は2年も保たない。わしなんか、これまでいったい何台のテープレコーダを潰してきたことか。
|
| ひろ子: |
でも、あんまり安物で音が悪くても駄目なんですよね? |
| 五反田: |
その通り。コピーする時にはただ単に聴いてるよりも、フレーズを口ずさんだり、一緒に楽器を弾いたりするとより、採りやすくなるぞ。
例えばこんなフレーズでも地道に一音づつ拾っていけばコピー出来るんじゃ。
仮に途中の音がわからなければ、まず何個、音が鳴ってるかを数える。
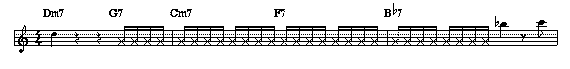
それぞれの16分音符の最初の音だけ、拾ってみる。
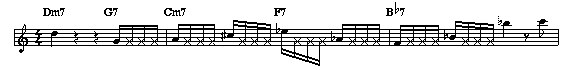
そのほかの音も解る所から次々に埋めていく。
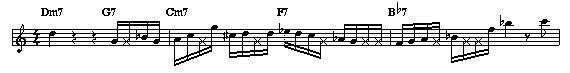
どうしても音が解らないところは前後から予想して、テープと一緒に楽器を弾いてみて、「この音かな? これかな?」なんて具合に、全部の音を埋めるんじゃ。
|
| ひろ子: |
ひ〜ぃ! 死にそう!
そんな細かいところまでコピーする必要ってあるんですか?
|
| 五反田: |
16部音符でバラバラ速弾きしてるような所は、初心者の場合、実際に自分で弾けないわけだから当面の間は無視しても仕方がないじゃろうが、8部音符の合間・合間にパラパラっと弾いてるやつはコピーしといたほうがいい。
こういう何気ないところにそのプレーヤーの癖や個性が出てたりするんじゃ。
|
| ひろ子: |
博士が前に言ってた、「こぶし」みたいな部分もそうですよね。 |
| 五反田: |
こういうのが「こぶし」の例じゃな。
例えばこんなフレーズでも地道に一音づつ拾っていけばコピー出来るんじゃ。
で、そうやって採った音を楽譜に書いていく。
|
| ひろ子: |
前にも、自分で作ったソロを楽譜に書け、って言われましたけど、楽譜に書く必要はあるんですか? |
| 五反田: |
大いにある!。
ひとつはメモとしてあとから見てすぐ思い出せるようにじゃが、もうひとつ「音を見る」ために楽譜を書く必要があるんじゃ。
|
| ひろ子: |
「耳を鍛える」の次は「音を見る」ですか? |
| 五反田: |
音は「聴く」ばかりじゃわからん部分があって、楽譜を目で見ることで見えてくるというか、非常にわかりやすいこともあるんじゃ。次の楽譜を見てごらん。

ちょっと離れて見ると音符の上がり・下がりの傾向や密度の濃い・薄いがわからんか?
|
| ひろ子: |
音符が生き物のように見えますね。 |
| 五反田: |
そうじゃろう。ここはちょっと音が込んでて、ここは空いてるとか、そういう全体的なことは音を聴いているだけじゃなかなか分からんものじゃ。 |
| ひろ子: |
「木を見て森を見ず」ってやつですね、博士! |
| 五反田: |
君はことわざ娘かね。
それ以外にもクセみたいなものも発見出来たりするんじゃ。「この人は半拍前始まりフレーズが多い」とか「休符が少なくて音を詰め込んでる」とかね。
|
| ひろ子: |
自分のソロを楽譜にすると自分でも気づかないクセなんかもわかっちゃうんですね。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ。「フレーズがいつも上がっていくばっかりだ」なんてことも... |
| ひろ子: |
博士! それってわたしのことですか!
3番目の「曲の構造やコード進行だけをコピーする」っていうのはどういうことですか?
|
| 五反田: |
これはコピーと呼べないものかもしれないが、例えば自分のバンドで「この曲をやってみようかな?」というときに、わしがやってるものじゃ。
バンドで演奏するためにはテーマが何小節で、アドリブのコード進行がどうなっていて、ここにこういうキメがあって、なんていうことを把握しなきゃならない。そういう時に音符ひとつひとつを全部コピーするわけではないが、全体的にスケッチするような感じでコピーするんじゃ。
|
| ひろ子: |
Real Bookとか「1001」とかは使わないんですか? |
| 五反田: |
わしは自分でコピーして、ピアノでいろいろ弾いてみて、自分でそれなりに納得いかないと気が済まないもんでな。「まつバンド」のリード・シートの大半はわしが書いているが、それもそんな理由だからじゃよ。 |
| ひろ子: |
でもそれはそれで大変そう! やっと4バースの感覚がわかったわたしにとっては.... |
| 五反田: |
まあ、これはひとえに訓練というか、経験じゃな。
さっきも言ったが、まず最初にコード進行をコピーしないと話が始まらん。で、次はそれがどんな順番で構成されているかを聞き取っていく。いわゆる伝統的なジャズは構成が簡単じゃが、今はやりのジャズはテーマとアドリブのコード進行が違っていたり、結構複雑でな。
まあ、コード進行だけなら楽器がなくても大体のところは聴いてりゃ分かるけれど。
|
| ひろ子: |
わたしは絶対音感がちょっと怪しいから、厳しいかな。 |
| 五反田: |
実はわしは全くと言っていいほど絶対音感はないのじゃ。そのかわり「相対コード感」とでもいうようなものを身につけとるんでな。
そうじゃ、今度、機会があったら「相対コード」を表現する方法についても説明しよう。
|
| ひろ子: |
今度って、いつなんですか? あと2回で終わっちゃうのに。 |
| 次回はちょっと閑話休題。パソコンを使ったジャズの練習方法を紹介しましょう。今回はコピーの素材として使用したデータをお楽しみください。誰の何の演奏かって? それは聴いてのお楽しみ!
|
| つづく |