1.この曲について
Estate(エスタテ)は、イタリア人のシンガー・ソングライター的なBruno Martino(ブルーノ・マルティーノ)が作曲し、自ら歌って1960年にヒットさせたポップス曲です。
ジャズマンに取り上げられることも増えてきて、新しいスタンダードになりつつあると言えるでしょう。その一方で、新しいが故の宿命なのか、キーや演奏スタイルが固まっていないという問題があるわけです。
曲としてはA(14)-A(14)-B(14)-A(14)で56小節という、ちょっと変わった小節数の曲ですが、聴感上の違和感はあまりありません。ブルーノ・マルティーノのオリジナルはスロー・バラードなので、小節数は半分になりますが、João Gilberto(ジョアン・ジルベルト)がボサノヴァで歌ったくらいから、倍の尺で数えるのが標準になったらしいです。
ぼくの手持ちの音源を中心に、キーや演奏スタイル、構成などをまとめてみましょう。実際の音源については、各自、検索して下さい。
年代順に並べてみましたが、割とぼくの好きな系のテナーものが多いですね。っていうか、そういうCDしか買わないからだろう! リズムはほぼBossa Novaですが、ゆっくりからミディアムまで幅があります。問題にしたいのは、キーと構成の列。
キーは何故かBm(ロ短調)が多数派です。Real Book 3や黒本もBmです。オリジナルは自分の声に合わせてDm(ニ短調)にしたんだろうし、ジョアン・ジルベルトも声とギターの弾きやすさなどからBmにしたのでしょう。一方、バーガンジやリーブマンはGm(ト短調)というフラット系のキーで演奏しています。そもそも、オリジナル重視というなら、Dmでやればいいんだし、何も好き好んでBmで演奏する義理はないわけです。
さて、上表の中では、19歳の時にローマで録音し、その後、ライブなどでも度々演奏していた、Michel Petrucciani(ミシェル・ペトルチアーニ)が、この曲を世界に知らしめたと言えるかも知れません。そうするとBmが「正解」と言ってもいいかぁ。
ペトルチアーニは名前だけ見るとイタリア人っぽいですが、イタリア系フランス人というのが正しいらしい。ただ、そう意味ではイタリアのポップスを取り上げたのも頷けるでしょう。最初の録音では随分、ゆっくり演奏していましたが、年々、テンポが速くなってきました。また、後半部分に違うコード進行を付けて、延々とコーダをやるようになっていきました。
もう一つの構成問題。何故「A-A-B-A」と「A-A-B」の2種類が存在するのか、何故、全員「A-A-B-A」で演奏しないのか。
それはAとBのメロディー・ラインとコード進行を見れば分かります。
シンプルにしたメロディ(Cmに変換済み)
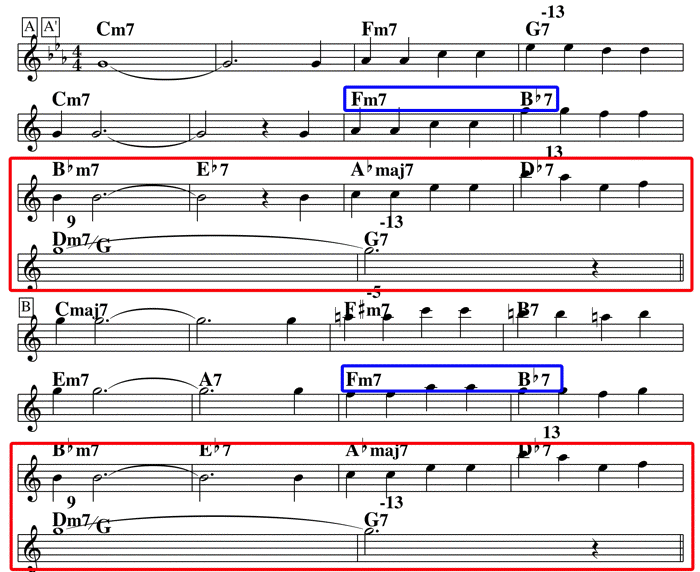
最後の6小節が全く同じメロディーなのです(赤い枠)。ついでに言えば、その前の2小節のコード進行も同じ(青い枠)。つまり、都合8小節のサウンドが同じということ。元来、A-A-B-Aはジャズで何コーラスも繰り返す場合、Aが3回続くことになる形式なワケで、この曲の場合、余計に強調されることになります。それが、A-A-Bで演奏する理由かと想像します。
2.参考テイク
で、結局、参考テイクはどれ?、というわけで、恥ずかしながら自分の演奏を紹介します。
キーはBmなわけなく、Cm(ハ短調)にしました。もちろん構成はA(14)-A(14)-B(14)です。リードシートを載せておきます。
リードシート
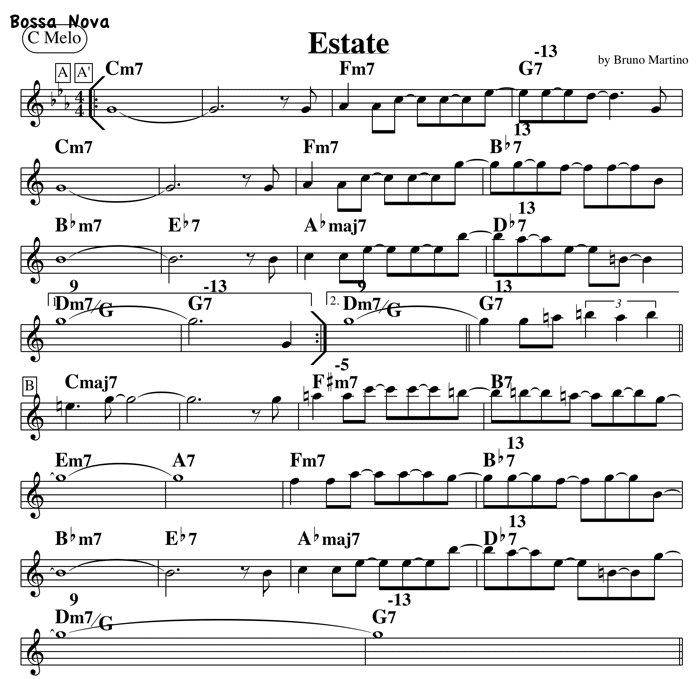
メロディーのシンコペーションが、ぼくの吹き癖のままになっているのはご愛敬。この曲で考え抜いた末に編み出したのは、A、Bの共通である最後の2小節のコード。
1回目のA
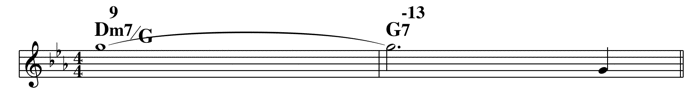
2回目のA
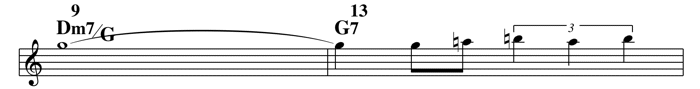
要するにドミナントであるG7を如何に処理するか、という話で、通常であれば「Dm7-5 - G7」とするところですが、ペトルチアーニの演奏を聴いていると、F♯713と弾いていました(半音上げるとG713)。13thに当たる、E♭(ミ♭)半音上げるとE(ミ)が気持ちいいなぁと。これをドミナント・ルートのII-Vにして、しかもDm7-5ではなくDm79にして(9thがミ)にしたわけです。次にCmに行く1回目のAはG7-13を使い、次にCmajに行く2回目のAではG713にするという芸の細かさ(笑)。アドリブはG7一発なんだけどね。
なんでこんな細かいところが重要なのか、と言われそうですが、吹いてて気持ちが上がるんだもん。
5.いざ、セッションへ
以上を踏まえ、これをジャム・セッションで演奏してみましょう。構成がA-A-Bであることはしつこい位に強調して下さい。14小節ずつではあるけれども、そんなに違和感は感じないと思います。
それでは、良きセッション・ライフを。