1.曲と参考テイクの説明
Frederick Loewe(フレデリック・ロウ)作曲のAlmost Like Being in Love(オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラブ)です。フランク・シナトラやナット・キング・コールの歌が有名らしいです。A(8)-A(8)-B(8)-A(12)の36小節で1コーラスで、標準的な曲より4小節多いのが特徴。黒本とNew Real book3に載っていますが、どちらもキーはB♭(変ロ長調)。楽器で演奏する曲は、キーが一つに固まることが多いのですが、この曲はバラバラです。ぼくが知ってるところをざっと表にするとこんな感じ。
特にコレ、っというものがないのがキーがバラつく理由なのかしら。
今回、参考にするのは、またこちら。まるでロリンズ・マニアのように思われるかも知れませんが、誤解のないように申し添えておくと、ぼくはロリンズが嫌いです。ロリンズ嫌いが敢えて勧めているわけだから、間違いないでしょ?
1953年10月7日録音のテナー + MJQによる演奏です。キーはE♭(変ホ長調)。
2.参考テイクのツボ
特にないのですが、敢えて挙げれば、コード進行の相違。キーをE♭に直した黒本とNew Real Book Vol.3のコード進行を載せます。
些細な違いはありますが、だいたい一緒です。唯一、決定的に違うのが、Bの最後。黒本の方は「スムーズに繋げました」みたいに見えますが、ポイントが曖昧というか、トーナリティーがCm(ハ短調)である時間が短く、次のサブ・ドミナントであるA♭にも繋がっていないという残念な進行になっています。一方、New Real BookはCmのトーナリティーを維持している感じで、次のA♭にも半音進行で繋がっている進行です。
ロリンズの演奏を聴いてみると、Cmのトーナリティーを維持しつつ、次のA♭にスムーズに繋げる工夫が見られます。音源を聞いてみましょう。
最初のテーマのBの2段目
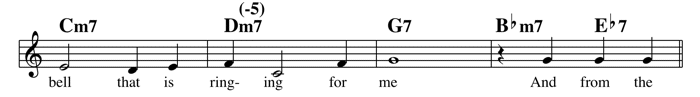
テナーソロのBの2段目

テナー譜で
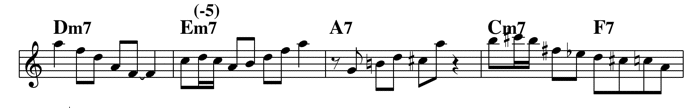
バイブソロのBの2段目
ピアノソロのBの2段目
ベースラインやピアノのコンピングからコード進行を割り出してみるとこんな感じ。
Dm7は ベースがA(ラ)を弾いていて、ピアノがA♭(ラ♭)を弾いていてDm7-5にも聞こえます。最後はA♭に繋げるために、B♭m7-E♭7にしています。ぼくはこれを採用したい。これを踏まえたリード・シートがこちら。
3.いざ、セッションへ
エンディングをどうしましょうか。ロリンズはストレートにそのまま吹いて終わっています。Ⅲ-Ⅵ-Ⅱ-Ⅴで伸ばしても良いですが、A"の最後8小節を繰り返してもいいですね。その際には演奏前に伝えておいた方が良いです。