| 今一度、ブルースを見つめてみましょう。 |
| ひろ子: |
博士〜、以前、ブルースを演奏するときは8小節目にだけ、注目しなさいって、おっしゃってましたよね。私もそろそろ初心者から一歩、踏み出そうとしてるので、次のアドバイスをいただければと思うんですが... |
| 五反田: |
「第1部 第4話」だったっけ? とりあえずロックなんかのブルースとジャズのブルースはどこが違うか、という観点から8小節目のVI7(6度7th)のフレーズなんかを紹介したんだっけ。 |
| ひろ子: |
Fのブルースで「ファ#」や「ミb」を使ったフレーズを弾くといいと教わりました。例えばこんなフレーズとか。
|
| 五反田: |
ブルースは人それぞれのアプローチで演奏するものなので、あまり「こう演奏しなさい」みたいなことは言いたくはないんじゃが。まあ、アイディアのひとつとして参考にしてもらおうか。
2番目のツボとしてわしが考えるのは4小節目じゃ。
|
| ひろ子: |
サブドミナントへ行く直前、ということですか? Fのブルースなら「Cm7-F7」です。
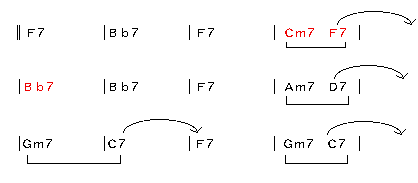
|
| 五反田: |
例えばこんな感じじゃ。
このままじゃ、あまりにもストレートじゃから、ちょっとオルタード・テンションを交えると頭よさそうなフレーズになるじゃろう。
|
| ひろ子: |
ほんのちょっと音程が変わっただけで、本当に半音違うだけでガラリと雰囲気が変わるんですね。テンションの力は偉大です。
F7のテンションはBbの「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」で考えるんでしたよね。
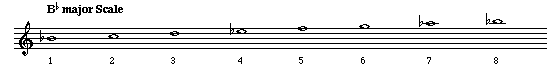
それを「ファ」から並べて数えていきます。
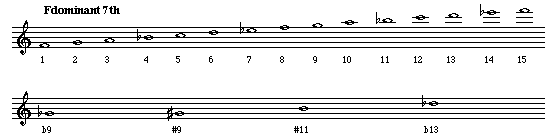
9thは「ソ」だからフラット9thは「ソb」、シャープ9thは「ソ#」、シャープ11thは「シ」、フラット13thは「レb」です。
ふ〜、テンションを数えるのに一苦労です。
|
| 五反田: |
間違って欲しくないのは、テンションのひとつひとつの音が大事なのではないということ。テンションを使いがらそれらがメロディーの流れとして一時的に違うトーナリティー(調性)を感じさせることが重要なんじゃ。 |
| ひろ子: |
はい、わかりました。
もう一つぐらいツボを教えてください。
|
| 五反田: |
ん? しょうがないな。じゃあ、レアなパターンではあるけれど、たまに使うと効果的というのを伝授しよう。かのマイルス・ディビスがまだチャーリー・パーカーと一緒に演奏していた頃のソロじゃ。
「イモなマイルス」として歴史的にも有名なソロじゃが、わしはそれほどイモとは思っておらん。むしろパーカーとは全く異なるアプローチでチャレンジしていると思う。特に「Bb7」での#11(シャープ11th)を強調したフレーズは特筆すべきものじゃ。
|
| ひろ子: |
あんまりブルースブルースしてないですね。幻想的というか浮遊感があるというか、不思議なサウンドがします。 |
| 五反田: |
まあ、それがマイルスの狙いであったんじゃろう。 |
| ひろ子: |
もう一度、テンションを調べてみましょう。え〜っと、BbですからEbの音階で考えます。
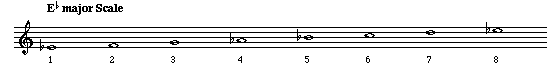
それをBbから並べて数えていきます。
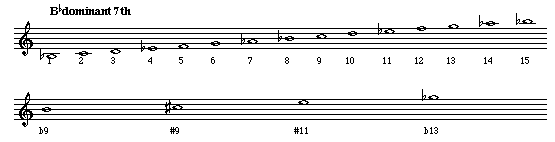
#11thは「ミ」ですね。
|
| 五反田: |
もうひとつ「Bb7」で#11を使ったフレーズを紹介しよう。
|
| ひろ子: |
こんな風に博士にいろんなフレーズを教えてもらってるんですが、これを自分のアドリブで使おうと思ってもなかなか上手くできないんですよね〜。 |
| 五反田: |
そりゃそうじゃ、そう簡単にできるわけがなかろう。
こう言うと誤解を招くかもしれんが、アドリブをするということはそれまで自分が練習してきたフレーズやアイディアをその場の展開に合った形で演奏するという面がある。そしてそのためには、それらのフレーズがいつ何時でも自由に引き出せるようにしなければならない。
|
| ひろ子: |
タンスの引き出しから春モノ・夏モノ・冬モノをさっさっ!と引き出すように、ですね。でもそのためにはきちんと整理しておく必要があります。 |
| 五反田: |
それはフレーズでも一緒で、コピーしたフレーズなどを自由に使おうと思ったら、そのフレーズがどういう音を使っていて、どういう場面で使えるかを研究しておく必要があるんじゃ。 |
| ひろ子: |
先ほどのBb7のフレーズは#11thを使っていて、ブルースの5〜6小節目に使えるということを把握しておくんですね。 |
| 五反田: |
いやいや、もっと深く広く理解しておくんじゃ。さっきのフレーズの「ミ・ド・ラb・ミ」は「#11th・9th・7th・#11th」の音を使っていて、Eオーギュメントの分散になっているとか、#11thを強調するような場面で使える、みたいにね。
理解したあとはそれを自由自在に扱えるように、何回も何回も繰り返して練習するんじゃ。
|
| ひろ子: |
はあ、それこそ「指クセ」になるほど、弾き込まないとアドリブの瞬間、瞬間に弾けませんよね。何か効果的な練習方法みたいなものはないんでしょうか? |
| 五反田: |
ん〜ん、そうじゃな、わしが昔よくやったのは「このフレーズ、絶対に使ってやるぞ!」法じゃ。 |
| ひろ子: |
何なんですか、その「このフレーズ、絶対に使ってやるぞ!」法というのは(笑)。もしかして文字通りの意味じゃないでしょうね。 |
| 五反田: |
実はそうなんじゃが(-_-;)。例えば次のようなフレーズがある。
ブレイクからソロを始めるときなどにも使えるフレーズじゃ。本来は2拍ずらしたこちらのフレーズなんじゃろうがね。
このフレーズにはマイナー版もあって、「Dm」に解決するところではこうする。
|
| ひろ子: |
特にオルタード・テンションはない、オーソドックスな音使いですが、解決色の強いフレーズですね。 |
| 五反田: |
このフレーズのメジャー版とマイナー版を可能な限り使ってアドリブしてみるんじゃ。例えば「I'll Close My Eyes」で考えてみよう。 |
| ひろ子: |
コード進行で見ると赤い文字のところで使うんですね。
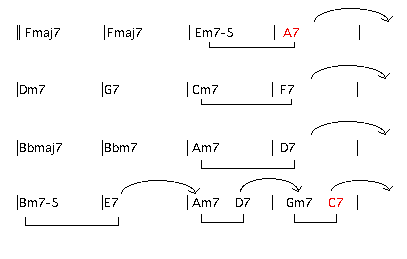
|
| 五反田: |
そうじゃ。この場所に来たら必ずさっきのフレーズを演奏するんじゃ。 |
| ひろ子: |
「このフレーズを絶対に使ってやるぞ!」と意識してですね。 |
| 五反田: |
さらにフレーズのキーを変えることで使える場所が増えるんじゃ。Bbmaj7に解決する「Cm7 - F7」ではメジャー版を使う。
さらに4段目の「Bm7-5 - E7」ではマイナー版が使える。
|
| ひろ子: |
4カ所に増えました。
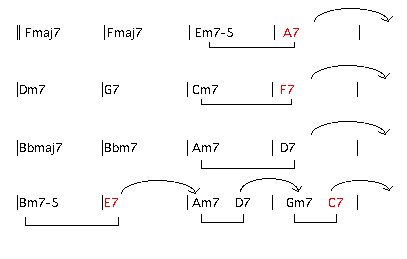
通してみるとこんな感じです。
博士〜!、これじゃメロディーがスカスカでアドリブになりません。
|
| 五反田: |
そりゃそうじゃ(笑)。でも最初は途中、全部、休符で目的のフレーズだけを弾く練習をすればいいじゃろう。カラオケなどに合わせて何コーラスも弾いていくうちに、タイミングなども体に染みついてくる。そしてだんだんに間を埋めるようにしてはどうかな、こんな具合に。
|
| ひろ子: |
間を埋めるのもちょっと相当猛烈に大変そうですが...(-_-;)
でも、そういう地道な努力が必要なんですね、やっぱり。
|
| 五反田: |
まあ、そう気を落とさずに。
今日は特別じゃ、「すぐに使えるフレーズ集」を紹介しちゃおう。最初は思いっきりシンプルなやつを。
|
| ひろ子: |
普通のダイアトニック・スケールのような気がしますが...あっ!、「ド・シ・シb」とここだけ半音で下がってます。 |
| 五反田: |
その通りじゃ。まあ、特にどうということのないフレーズじゃが、ドミナントから半音・半音で下がってあとはダイアトニックに下がってくるだけで、ちょっとだけズージャの香りがするじゃろう。Wayne Shorterの昔の演奏を聴くと出てくるぞ。 |
| ひろ子: |
こういうシンプルなフレーズもアリなんですね。目からウロコもんです。 |
| 五反田: |
次はもう少しジャズっぽいやつで、「サブ・ドミナント−サブ・ドミナント・マイナー」の進行で使える。
譜割りを変えたこのパターンもよく使われるフレーズじゃ。
|
| ひろ子: |
よく聞くフレーズです。使ってる音は9thとコード・トーンだけの、殆ど分散和音だったんだあ! 改めて基礎の大事さがわかりました。 |
| 五反田: |
実はこれはそのままドミナントでも使えるんじゃ。
|
| ひろ子: |
あ〜、本当だ! C7上ではテンションを含んだフレーズになるんですね。 |
| 五反田: |
それはちょっと的が外れている。ここでは「Gm7-C7」を「Gm7-Bbm7」というコード進行に置き換えたところから発想しておるんじゃ。つまりC7として弾いているんじゃなく、Bbm7のつもりで弾いてるんじゃ。だからC7上のテンションがどうしたこうしたという分析は正しくない。
またまた、全く同じ音でマイナーの場面で使うことも出来るんじゃ。
|
| ひろ子: |
全く同じフレーズで3種類のコード進行で使えるなんて、なんてお得なフレーズなんでしょ。 |
| 五反田: |
いやいや、まだまだあるぞ。これの発展型というか応用型で、より緊張感を増したフレーズもあるんじゃ。
|
| ひろ子: |
全く同じ譜割りで、音使いも同じですが、全体的に短3度上がっています。この場合はオルタード・テンションを含んだフレーズと考えていいんでしょうか? |
| 五反田: |
まあ、いいかもしれんが、それも所詮、あとから付けた屁理屈なようなところがある。実際に演奏するときは「Dbm7(C#m7)」の分散和音のつもりと考えた方が判りやすいかもしれんなあ。
上の二つの連続技なんてもアリじゃよ。
|
| ひろ子: |
一つのフレーズからいろんなバリエーションが生まれるものですね。 |
| 五反田: |
そうじゃ、一つのフレーズを自分で演奏してみて、フレーズの始まりを前後にずらしてみたり、経過音を付け加えてみたり、いろいろと試してみるといいじゃろう。
さあ、もう一つII-Vのフレーズを紹介しよう。
|
| ひろ子: |
かっちょいい! マイケル・ブレッカーみたいです〜。 |
| 五反田: |
いや〜、実はマイケル・ブレッカーの得意フレーズなんだけど...(-_-;)
今日紹介したフレーズや自分でコピーしたフレーズを分析して、繰り返し練習して自分のものにすることじゃ。
|
| ひろ子: |
やっぱり、いろんなキーで出来るようにした方がいいんですよね? |
| 五反田: |
うん、それはそうじゃ。管楽器などは音域の制約があるので厳しい場合もあるが、Any Keyで弾けるのに越したことはない。
ただ、あんまり高望みして結局ものになりませんでした、じゃあしょうがない。最初はキーがFのフレーズだけでもいいじゃないか。出来ることからコツコツとやればいいじゃないか。
|
| ひろ子: |
はい、わかりました。地道に練習してフレーズの引き出しを増やしていきます。 |
| みなさんもどんどん引き出しを増やしてください。次回はアドリブのアプローチの色々についてお話ししましょう。 |
| つづく |