| 今回はデューク・エリントンの名曲「Satin Doll」にひろ子が挑戦! |
| 五反田: |
ひろ子くん、「Satin Doll」は練習してきたかね? |
| ひろ子: |
はい、アドリブは何とか、なりそうなんですが、テーマをどうやって弾いたらいいか、悩んでいます。単音でメロディを弾いてもショボくって。 |
| 五反田: |
確かにそれは言えてるね。管楽器ではストレートにメロディを吹くだけでもサマになるのに。ピアノでテーマを取るときの永遠のテーマかもしれない。 |
| ひろ子: |
何かいい方法はないんですか? |
| 五反田: |
例えばシアリング風に和音で弾いてみるとか... |
| ひろ子: |
シアリング風?
あ!、「第2部 第4話」の「Softly As In A Morning Sunrise」や「Take The A Train」で博士が弾いたパターンですね。
ところで「シアリング」って何ですか?
|
| 五反田: |
シアリング・サウンドとは盲目のピアニスト−ジョージ・シアリングという人が自分のクインテットで演奏していたスタイルで、具体的にはこんなサウンドじゃ。
シアリングはこのサウンドをラテン・ビートに乗せても演奏しておる。
例えばこの技法を使えばどんな曲でも「ジャズ」になると言っても過言ではないんじゃ。松田聖子ちゃんの「Sweet Memories」なんかもこんな風にアレンジできる。
|
| ひろ子: |
へえ〜、特徴的ではありますが、耳障りのいい音ですね。商店街のBGMで流れてるみたいな。 |
| 五反田: |
その指摘はある意味、非常に正しい。どんな曲をも「ジャズ」に出来るかわりになにをやっても似通った、そう、室内楽的な「お上品な」サウンドに仕上がってしまう。 |
| ひろ子: |
そんな「シアリング・サウンド」の何を学べばいいんでしょう? |
| 五反田: |
正確には「シアリング・サウンド」を学べというより、「シアリング・ボイシング」を学べと言うべきだったかな。理論書によっては「ブロック・コード」の一種、なんて書いてある場合もある。 |
| ひろ子: |
「ボイシング」というと「和音の積み重ね方」ということですよね。「シアリング・サウンド」ではピアノだけが和音を弾いているように聞こえましたが。 |
| 五反田: |
そうじゃ、このサウンドに於けるピアノのボイシングを勉強するのが、アレンジへの第一歩になるんじゃ。
まず、「シアリング・サウンド」の基本的な構造から見てみよう。
さっきの「East Of The Sun」の冒頭部分を例に取ると、ピアノ、バイブ、ギターでこんな風に弾いておる。
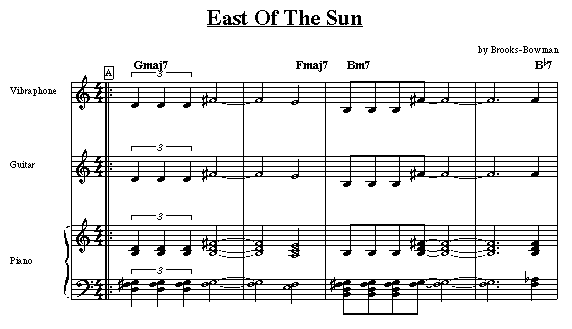
|
| ひろ子: |
ギターとバイブは同じ音を弾いてるんですね。 |
| 五反田: |
ここではギターは1オクターブ上げて書いてあるので、厳密にはギターとバイブはオクターブでユニゾンしているんじゃ。
もっと言うと、バイブはピアノのトップノート(一番高い音)と同じで、ギターはピアノのボトム・ノート(一番低い音)と同じ。そのオクターブの間をピアノが埋めているというボイシングなんじゃ。
|
| ひろ子: |
あ、本当だ! ピアノは5声ですが、トップとボトムがオクターブ違いなんですね。ん? ということは随分と密集した和音になりますよ〜。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ。こういうボイシングのことを「クローズド・ボイシング」と言うんじゃが、実は「シアリング・ボイシング」の起源は伝統的なビッグ・バンドのサックス・セクションにあるんじゃ。
例えば有名なグレン・ミラーの「ムーンライト・セレナーデ」のサックス・セクションはこんな感じ。
これをそっくりピアノで弾いて、トップ・ノートをバイブ、ボトム・ノートをギターで弾くと、そのまま「シアリング・サウンド」になるんじゃ。
|
| ひろ子: |
本当だ! 意外と簡単なんだあ〜 |
| 五反田: |
そうそう、簡単なんじゃよ。じゃあ、やってみようか。 |
| ひろ子: |
はい!。ん? ちょ、ちょ、ちょっと待って下さい。肝心のピアノでどんな和音を弾くのかが判りません。 |
| 五反田: |
おう、おう、そうじゃった。じゃあ、実際に「Satin Doll」のテーマをシアリング・ボイシングしながら説明しよう。
メロディーはこんな感じじゃろう。
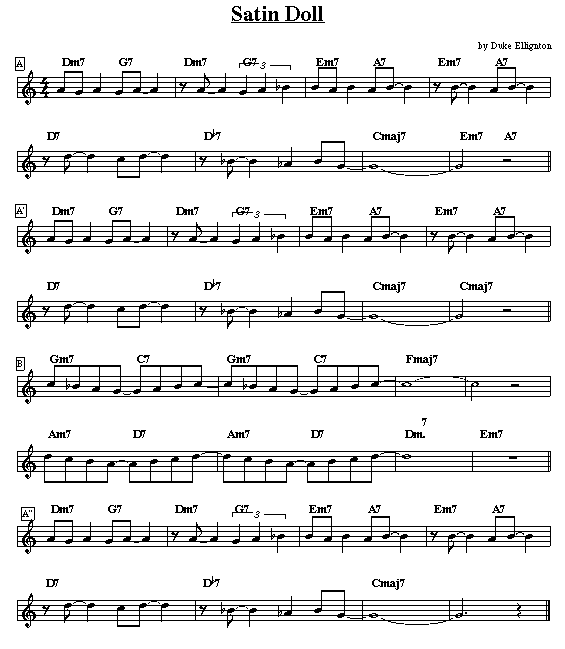
最初の音は「ラ」で、これをDm7でボイシングする。逆に言うとDm7を「ラ」をトップ・ノートにして展開するんじゃ。
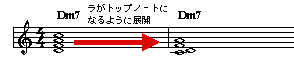
|
| ひろ子: |
「第3展開形」ってやつですね。昔、エレクトーンで習いました。 |
| 五反田: |
第3か第1かはよく判らんが、要は展開形じゃ。で、このときのDm7はテンションなんぞ、な〜んにもない、ベタのDm7、「レ・ファ・ラ・ド」で弾くこと。「ルートのレは省いて...」なんて余計なことを考えないのがポイントじゃ。この4音にオクターブ下の「ラ」を加えて、ハイ、出来上がり。
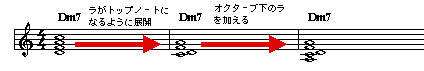
次の「ソ」はちょっと飛ばして、次の「ラ」も同じDm7で同じ和音でいい。次の「ソ」はコードがG7なのでG7のコード、つまり「ソ・シ・レ・ファ」を「ソ」がトップノートになるように展開する。
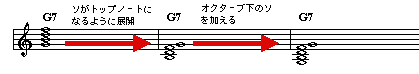
次の2小節は前の2小節をそのまんま全音上げただけで考え方は同じじゃ。だから最初の4小節は、こんな風になるじゃろう。
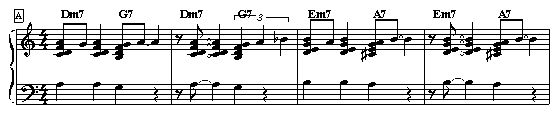
|
| ひろ子: |
博士! 和音になっていないところはどうやってハーモナイズするんですか? |
| 五反田: |
よく見て欲しいんじゃが、上で和音にした所はメロディー・ラインがコード上の構成音、コードトーンになっているんじゃ。 |
| ひろ子: |
あ!、本当だ。「ラ」はDm7中に含まれるし、「シ」はEm7の中の一音です。 |
| 五反田: |
こういうコードトーンをハーモナイズするのは比較的簡単なんじゃ。問題はコードトーン以外の音、例えば2番目の「ソ」。コードはDm7だから「ソ」は含まれておらんじゃろう。 |
| ひろ子: |
こういうのをテンションって言うんですか? |
| 五反田: |
時と場合によるが多くの場合、テンションとは言わない。経過音とかアプローチ・ノートなどと呼んでおる。そしてこのアプローチ・ノートをいかにハーモナイズするかにちょっとしたツボがあるんじゃ。 |
| ひろ子: |
早くそのツボを教えてくださ〜い! |
| 五反田: |
よ〜し、とっておきのツボを伝授しよう。
アプローチ・ノートをハーモナイズするツボ其の一
それは動かさない!
|
| ひろ子: |
えっ! 「動かさない」ってどういうことですか? ま、まさか... |
| 五反田: |
ご察しの通り、前後と同じ和音で押し通してしまうというのが第一のツボじゃ。
例えば1小節目、メロディーは「ラ・ソ・ラー・ソ・ラー」の「ソ」や「ラー」は前後の和音のトップとボトムの音だけを変えるんじゃ。
1小節目(d9m12.mid)
メロディーと全音でぶつかってしまう2番目のファや5番目のシは省略しても構わない。
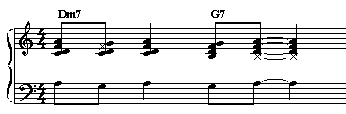
|
| ひろ子: |
特に低い方で隣接した音を鳴らすとサウンドが濁りますからね。
次のツボは何ですか?
|
| 五反田: |
ツボ其の二はドレミファソラシドじゃ! |
| ひろ子: |
またまた、何の事だか判りましぇ〜ん! |
| 五反田: |
つまりメロディーが「ソ・ラ・シ」と上がったらハーモニーも一緒に「レ・ミ・ファ」と上がるということ。モノの本によれば「ダイアトニック・アプローチ」なんて言っているのもある。
2小節目の3拍目のメロディーが「ソ・ラ・シb」と上がるところはこれを使おう。
| ソ |
→ |
ラ |
→ |
シb |
| ファ |
→ |
ソ |
→ |
ラb |
| レ |
→ |
ミ |
→ |
ファ |
| シ |
→ |
ド |
→ |
ド# |
| ソ |
→ |
ラ |
→ |
シb |
「ラ」から「シb」へは半音上に上がっているから、あとの音も半音づつ上げてみよう。これは「クロマティック・アプローチ」と称しておる。
|
| ひろ子: |
だんだん本格的になってきましたね。メロディーがソ→ラ→シb→シと上がっていくので、ハーモナイズもその流れを重視するわけですか。 |
| 五反田: |
そういうことじゃ。ここまでのツボで1段目4小節はハーモナイズできるじゃろう。
問題は2段目のDb7。ここはちょっと例外的なハーモナイズだ。メロディーが「シb」というDb7の13thなのでこんな感じになるかな。
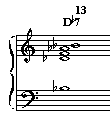
通常のボイシングではDb7(13)はこんな風に3rdと7thを弾くのが普通じゃ。
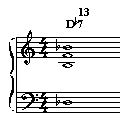
ところがクローズド・ボイシングである「シアリング・スタイル」では7thの「シ」と13thの「シb」が半音でぶつかってしまうため、「シ」を取り除いている。まあ、些細なことなんじゃが。
|
| ひろ子: |
急に話が難しくなってきました。とりあえずAの部分はこんな感じでできあがりました。
サビはどうしましょうか?
|
| 五反田: |
手法としてサビは雰囲気を変えてシングル・トーンでいくという手もあるが、ここではそのままシアリングを続けてみよう。
いきなりの「ド」がGm7のノン・コード・トーンじゃが、「ツボ其の一」を使って次の「シb」のボイシングを先取りしてしまえばいい。「シb」のあとの「ラ」は「ツボ其の二」を使って音階通りに降りてこよう。
ここでちょっと変化を付けるために2回目のC7に「ツボ其の三」を使ってみよう。
|
| ひろ子: |
微妙な違いですが、あとの方が胸がキュンとするような気がしますう。これが「ツボ其の三」なんですかあ? 和音上の「ド」が「レb」になっただけのようですが。 |
| 五反田: |
そうじゃろう。前にも言ったが「シアリング・ボイシング」ではなかなかコードトーン以外の音を使うのが難しい。唯一使えるテンションはフラット9thくらいなんじゃ。で、C7の「レb」がC7のフラット9thというわけ。
でもこのフラット9thのサウンドが「シアリング・サウンド」の重要なカラーなんじゃ。
だから「ツボ其の三 テンションはフラット9th」じゃ。
|
| ひろ子: |
サビの2段目はほぼ1段目の全音上げで出来そうですね。 |
| 五反田: |
そうじゃな。サビを通してみるとこうなるかな。
|
| ひろ子: |
最後のAはその前のAと一緒でいいですね。これで1曲完成じゃないですか!
ツボはこれで終わりですか?
|
| 五反田: |
もうひとつ、忘れてはならないツボがあった。
「ツボ其の四.困ったときのディミニッシュ」っていうやつじゃ。
|
| ひろ子: |
(????????) |
| 五反田: |
これもアプローチ・ノートのハーモナイズ方法のひとつなんじゃが、例えばサビのGm7でド・シ・ラ・ソと降りてくる時のラに適用してみよう。下の譜面で赤く丸印がついているところがそうじゃ。
|
| ひろ子: |
CdimというかEbdimというか、F#dim、Adimというか.... |
| 五反田: |
そうじゃ、ディミニッシュは4音すべてがコードネームになり得るからな。 |
| ひろ子: |
でもサウンド的にはあんまり区別が付かないような気がするんですが.... |
| 五反田: |
実はそうなんじゃ。こんな風に8分音符、1個分のボイシングを変えても全体的には些細なことになってしまうんじゃ。
でももう少し違ったメロディーでどうしてもアプローチ・ノートのボイシングに困ったときは、ディミニッシュでボイシング、というのが有効な手になる。
さらに言えば「ツボ其の三」で紹介したフラット9thとディミニッシュは義兄弟みたいなもんで、C7フラット9thとC#dimはサウンド的に同じなんじゃ。その意味では「ツボ其の三」と「ツボ其の四」は一つにまとめてもいいかもしれない。
|
| ひろ子: |
せっかくですから全部を聞いてみましょうよ。
全部シングルトーンで弾くのとでは全然印象が違ってきますね。
|
| 五反田: |
ついでだからバイブとギターを加えた「シアリング・サウンド」そのものも聞いてみよう。
|
| ひろ子: |
それにしても私は今まで、「シアリング・サウンド」っていう言葉は聞いたことがありませんでした。一般的なんでしょうか? それとも博士の独自理論とか... |
| 五反田: |
いやいや、極めて一般的じゃよ。ジャズ・ライフでも特集を組んでたくらい。
カシオペアの向谷くんなんぞは得意にしていて、キーボードでテーマを取る曲でよく使っておるぞ。
|
| ひろ子: |
まさか、カシオペアが出てくるとは思いませんでした。恐れ入りました。
それにしても今回はいっぱい曲が出てきましたね。ちょっと難しい言葉も出てきたし、ようやく「ジャズ講座」らしくなってきましたね。
|
| 五反田: |
なんじゃと〜、最初から立派なジャズ講座じゃい! |
| ひろ子: |
まあ、まあ、そう怒らないでください(-_-;)。
みなさん、今回は「Satin Doll」をシアリング・サウンドで練習してみてくださ〜い。
|
| さて、次回はいよいよ最終回。バンドの発表会に向けて、何をしたらいいかについてお話しします。 |
| つづく |