| ひろ子ちゃんが他流試合ともいうべきライブ・ハウスのジャム・セッションに挑戦しました。さて、その結果は... |
| ひろ子: |
博士〜!、このあいだ初めてライブ・ハウスでやってるジャム・セッションに行ったんですよ! |
| 五反田: |
お〜、それはチャレンジじゃったのう。 |
| ひろ子: |
やっぱり知らない人同士で演奏するっていうのは緊張しますね。弾きはじめたらアタマの中が真っ白になっちゃって、何を弾いているのか判りませんでした。 |
| 五反田: |
で、何を演奏したんじゃね? |
| ひろ子: |
「There Is No Greater Love」と「Blue Bossa」をやったんですけど、あとでテープを聴いてみて気がついたんですが、特に「There Is No Greater Love」で以前のわたしのような「チャカチャカ」した弾き方になっていたんですよ。 |
| 五反田: |
第1部第5話でわしが指摘した8分音符の「ノリ」の話じゃな。 |
| ひろ子: |
そうです。博士に言われてからいつも「音符を長く弾く」ことを心がけていたんですが、何故かこの時は元の自分に戻ってしまいました。そんなに速いテンポじゃなかったんですけど、余裕が全然なくなってしまって。やっぱり緊張してたのかなあ? |
| 五反田: |
それだけとも限るまい。「There Is No Greater Love」では誰がベースを弾いたんじゃ? |
| ひろ子: |
ジャム・セッションのハウス・トリオはいたんですが、その時は大学生らしい人がベースを弾きましたが、それがどうかしたんですか? |
| 五反田: |
その大学生の演奏を聴いたわけではないので断言は出来んが、ベースのノリの悪さがひろ子くんのピアノを狂わせた可能性がある。 |
| ひろ子: |
そんな! 単にわたしがヘタクソなだけですよ。 |
| 五反田: |
もちろん、ひろ子くんが絶対的に上手ければ誰がベースを弾こうがそれに左右されることもなかろう。じゃが、まだまだひよっ子のひろ子くんの場合は、一緒に演奏する人によって影響を受けてしまうんじゃ。特にベースはモロにバンド・サウンドやソロイストのノリに影響するから、ベースの上手い下手で演奏全体の出来が大きく変わってしまうことが多い。 |
| ひろ子: |
そういえばハウス・トリオのベースの方が弾いてくれた「Blue Bossa」はテンポが速かったんですけど、弾きやすかったです。 |
| 五反田: |
そうじゃろう、そうじゃろう。 |
| ひろ子: |
それは第一部第5話で教えていただいた「音符の長さ」の問題なんですか? |
| 五反田: |
それもあるじゃろう。再掲になるが「ノリのいいベース」と「ノリの悪いベース」の4分音符をシーケンサーのピアノ・ロール画面で見るとこんな風になる。
| ノリのいいベース |
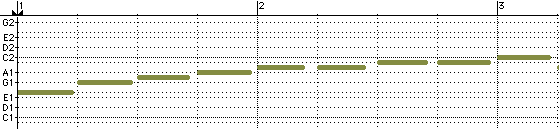 |
|
| ノリの悪いベース |
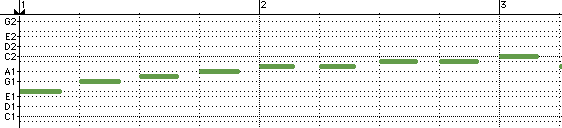 |
|
| ひろ子: |
「ノリのいいベース」の4分音符は長いんでしたよね。 |
| 五反田: |
さらにベースの場合は音の立ち上がり、音の伸びなどがスイング感に大きく影響するんじゃ。
ひろ子くんはこんな図を見たことがあるかな?
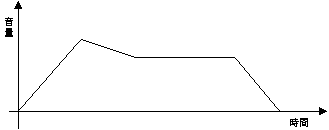
|
| ひろ子: |
あります、あります! 博士はご存じないかもしれませんが、今時のエレクトーンは音色を作ることが出来るんですよ。これはシンセサイザーなどで音を作るときに使うエンベロープです。別名ADSR曲線! |
| 五反田: |
その通りじゃ。
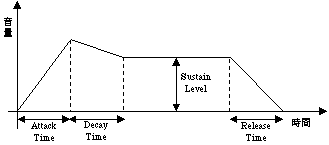
鍵盤を押してから音量が最大になる時間を決めるAttack(A)、そこから減衰する時間がDecay(D)、鍵盤を押し続けたときそのまま鳴り続ける音量がSustain(S)、鍵盤を離してから音が消えるまでの時間がRelease(R)ということじゃ。
実際の音は波なのでプラス・マイナスの振幅があるため、正確にはこのように表せる。
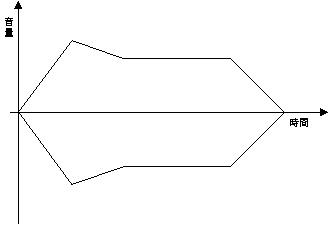
が、面倒だし判りづらいので上図のように半分の波形で表すんじゃ。
|
| ひろ子: |
ADSRを調整する事によっていろんな楽器のシミュレーションをするんですよね。
でもそれがベースのノリとどう関係するんですか?
|
| 五反田: |
ベースのエンベロープを考えてみよう。ベースは弦楽器だからSustainは0じゃな。またギターなどと比べてAttack時間が長いのが特徴じゃ。理想的なベースはこんな感じかな。
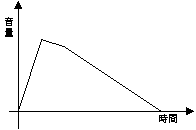
これが次の音に早く移ろうとして弦から左手を離してしまうと音がブチ切れになるのがこれ。
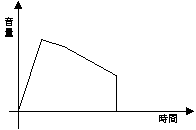
さらに左手の押さえが弱かったりして、音の減衰が早いパターンはこれ。
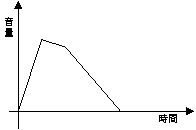
|
| ひろ子: |
わかります、わかります。2番目や3番目のベースじゃスィングしませんよね。 |
| 五反田: |
さらにAttack時間が長いと言うことは弦をはじいて、しばらくしてから音が鳴るということじゃろう。つまりジャストのタイミングでビートを出すためには1拍のちょっと前に弾きはじめて、音量のピークがジャストの位置に来るようにしなければならないんじゃ。図にするとこういう感じ。
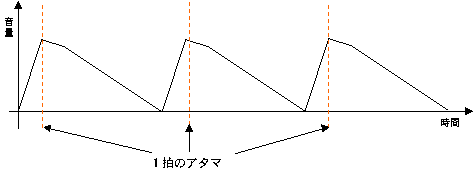
先ほどのシーケンサーのピアノ・ロールでの表示は厳密にはこんな感じになるんじゃ。
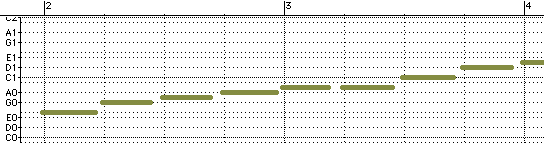
|
| ひろ子: |
え〜えっ! ベースの人ってそんな神業のようなことやってるんですかあ? 本当に? |
| 五反田: |
疑っとるな。じゃあ関くん、ランニングをやってみてくれ。 |
| 関: |
はい、わかりました。
|
| 五反田: |
これをハード・ディスク・レコーディング・ソフトで波形を見てみると、どうじゃ!
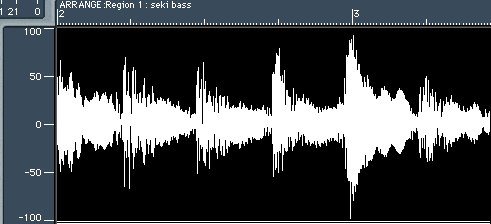
|
| ひろ子: |
上の一番大きな目盛と数字が小節数、ちょっと大きい目盛が1拍を表しているんですね。わあ、本当に博士の行った通りに、拍のちょっと前から弾きだして、ちょうど拍のアタマで音量がピークになっていますね! |
| 五反田: |
納得したかね? この結果、「ノリのいいベース」は「ブウォーン・ブウォーン」のように聞こえるんじゃ。
これを仮に1拍のアタマから弾きはじめると、下のグラフのように音量のピークがアタマから若干ずれてしまう。
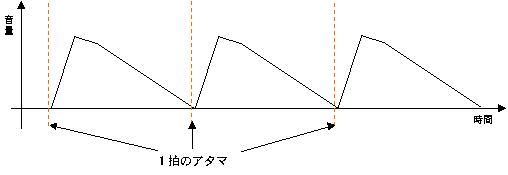
これでずーっと押し通してくれたならまだ何とかなるんじゃが、多くの場合、ビートが後ろ後ろに引っ張られて、その結果、テンポが遅くなってしまうんじゃ。
反対に次図のようにあんまりにも早く弾きはじめると、音のピークが拍の前に来すぎてしまい、結果的にテンポが速くなってしまう。
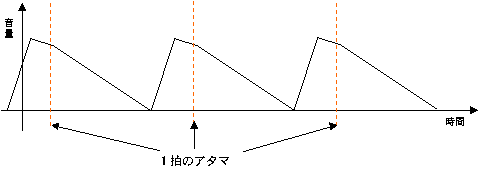
まあ、下手なベースは前になったり後ろになったりと安定しなくて、しかも音が短いケースが一番多いんじゃろうが。
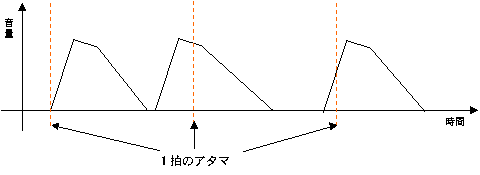
|
| ひろ子: |
でもそんなベースじゃあ、落ち着いてソロなんて取ってられませんね。 |
| 五反田: |
おおっ! 随分と高飛車に出たな。まあ、でもその通りじゃ。だからバンドを組むときには上手いベースを入れるのが一番。逆に言えば、上手いベースと練習すると上達も早い。 |
| ひろ子: |
なるほど、だから博士はベースに口うるさいんですね。
ところでそのジャム・セッションで「Blue Bossa」もやったんですが、あれはボサ・ノヴァというかサンバというか、ラテンですよね。ずーっと4ビートばかり練習してたんで、「ノリ」がいまひとつ判らなかったんですが、どういう具合にノレばいいんでしょうか?
|
| 五反田: |
やっと本題に入ってきたな。
こう言うと意外に聞こえるかもしれんが、4ビートと同じ感覚で弾けばいいんじゃ。
|
| ひろ子: |
まさか! いくら博士の言うことでもそればっかりは信じられません。 |
| 五反田: |
いやいや、本当じゃよ。例えば次のようなフレーズがあったとしよう。
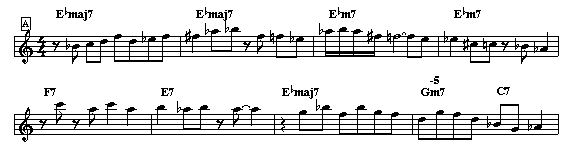
これをラテン・ビートをバックに演奏してみよう。
同じフレーズを4ビートをバックででも演奏しよう。
|
| ひろ子: |
ラテンでも4ビートでも違和感がないですね。微妙にノリを変えて弾いてるんですか? |
| 五反田: |
バックのサウンドを変えただけじゃよ。 サックスのパートは全く同じじゃ。
前にも言ったが、8分音符のノリは時代とともに変化している。例えばディキシーランドやスウィング時代の8分音符でもさっきのフレーズをやってみよう。
その古いノリで弾いたソロをバックをラテンに変えてやってみよう。
|
| ひろ子: |
これはちょっと違和感があります。どういうことなんでしょう? |
| 五反田: |
判りやすいようにまたまた、シーケンサーのピアノ・ロール画面で二つのサックス・パートを見比べてみよう。
| ラテン・ビートでもはまる8分音符 |
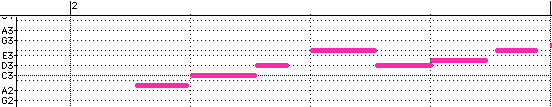 |
|
| ディキシーランド/スィング時代風の8分音符 |
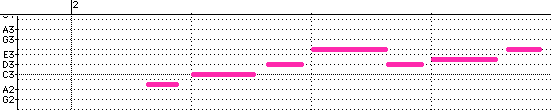 |
ピアノ・ロールだとちょっと微妙すぎて判りづらいかな? デジタルに数字で表してみよう。
| ラテン・ビートでもはまる8分音符 |
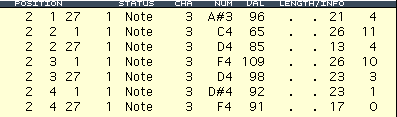 |
|
| ディキシーランド/スウィング時代風の8分音符 |
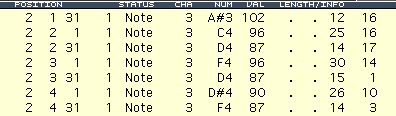 |
|
| ひろ子: |
これまた、判りづらいですが、「POSITION」の下に書いてある数字が小節・拍・拍中の位置を表しているんですね。
例えば「2 1 27」というのは2小節目の1拍目の27サブ拍目から音符が始まってるということですね。
|
| 五反田: |
ここでは1拍を48に分解しているから27サブ拍は27/48拍目ということじゃ。
も少し判りやすく説明しよう。「ラテン・ビートでもはまる8分音符」のほうは1拍を26と22に分割しておる。つまり8分音符のアタマとウラの比が約1.18:1、ほとんど1:1ということ。
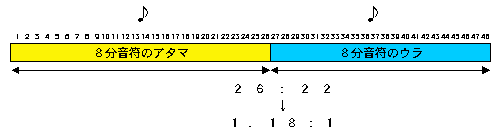
それに比べて「ディキシーランド/スウィング時代風の8分音符」は1拍を30と18に分けておる。8分音符の比は、ん〜と5÷3だから約1.67:1になるな。
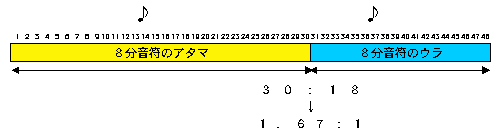
|
| ひろ子: |
よく言われる「4ビートでの8分音符は3連符の2つと1つ」というのは大ウソだったんですね。3連の2つと1つじゃ2対1ですものね。
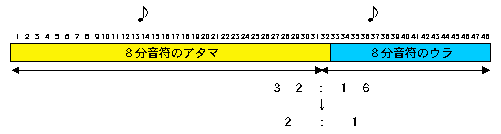
|
| 五反田: |
そのあたりのことは随分、前に話したことがあったな。「もっとオモテとウラの長さを揃えるというのか、ウラを弾くタイミングをもっと前にするというか、つまりはもっと普通の8分音符に近く弾かなければいけない。」みたいに。 |
| ひろ子: |
それも第1部第5話でしたよね。その時は抽象的な話で「そんなもんかなあ」くらいに聞いてましたが、こうして具体的に証拠を見せられると納得します。ハイ。 |
| 五反田: |
このように、古いジャズの8分音符は良くも悪くもルーズというか、「ターカ、ターカ」というようにアタマとウラの8分音符の長さが違うんじゃ。これが独特な「ジャジー」な雰囲気を出しているのは確かなんじゃが、今ひとつ鋭さに欠けるというか、甘さが残ってしまう。その甘さを排除するために、ビ・バップ、ハード・バップ、新主流派と時代が進むにつれて、どんどん8分音符のアタマとウラが均等になってきたんじゃ。逆の言い方をすると、8分音符を均等化することでジャズが進化してきた、と言ってもいいくらいじゃ。
さらに1970年以降、8ビートや16ビートが主流のフュージョンの時代を経て、ポスト・フュージョンとして登場した「新しい4ビート」ではその傾向が極めて強かった。いやむしろ、それをウリにしていたようなところがあった。
|
| ひろ子: |
Chick CoreaとSteve Gadd,Eddie Gomezの演奏やStepsの演奏ですよね。 |
| 五反田: |
そうじゃ、古いことをよく知っておるな。
わしが考えるに4ビートは円を描くようなイメージなんじゃ。それに比べて8ビートや16ビートは四角い(Square)イメージがある。「新しい4ビート」はその円と四角のギャップを埋めたと言えるんじゃなかろうか。
|
| ひろ子: |
4ビートと8ビート・16ビートのギャップが埋まるとどういうことになるんですか? |
| 五反田: |
曲中に4ビートから8ビート・16ビートに、あるいはその逆に8ビート・16ビートといったSquareなビートから4ビートに、というビート間の移動が自由になったんじゃ。 |
| ひろ子: |
確かに「チュニジアの夜」なんかの古い演奏で、ラテン・ビートから4ビートに変わるときに違和感があるというか、4ビートになった途端、気が抜けてテンポも遅くなるような感じがしますものね。 |
| 五反田: |
4ビートになると「チンタラチンタラ」するんじゃな。基本ビートが多い8・16ビートから4ビートになるとどうしても音がスカスカになって、スピード感が失われてしまいがちなんじゃ。
それが「新しい4ビート」では逆にスピード感が増すというか、アクセルをグイと踏み込むような快感を得ることが出来るんじゃ。
|
| ひろ子: |
Chick Coreaの「Samba Song」などはその良い例ですね。ピアノ・ソロの途中から4ビートになりますが、気が抜けるどころかますます緊迫感が増してました。途中、シャッフル気味のリズムになったりと、リズムの幅が広がりました。
その「新しい4ビート」で均等に近い8分音符で演奏するためには、どうすればいいんでしょうか? やっぱりソロイストが頑張るしかないんでしょうか?
|
| 五反田: |
確かにソロイストの力量も必要じゃが、ベース・ドラムスの役割も欠かせない。いやむしろ、新しいベース・ドラムスがあってこそ実現可能と言った方がいい。そしてそのベースは、最初に述べた「ノリのいいベース」でなければダメなんじゃよ。 |
| ひろ子: |
ようやく話が繋がりましたね。そういえばChick Coreaの諸作にしてもStepsにしてもベースはEddie GomezでドラムスがSteve Gaddでしたね。これは偶然なんですか? |
| 五反田: |
いやいや、偶然ではない。当時Eddie GomezはBill Evansトリオ出身のベーシストとして名を馳せていたが、Steve Gaddはフュージョン界の売れっ子ドラマーではあったが、「Gaddの4ビートは変!」なんて言われていたんじゃ。 |
| ひろ子: |
普通、4ビートでのシンバル・レガートは「チーンチキ、チーンチキ」ですけど、
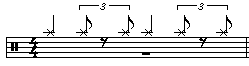
Gaddのシンバル・レガートは4分音符ですものね。
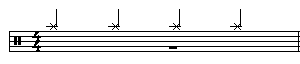
|
| 五反田: |
「チーンチキ、チーンチキ」もわしに言わせればウソなんじゃが....
4分音符のシンバル・レガートはTony Williamsがやっていたが、全面的にやりだしたのはGaddじゃろう。Gaddの場合、ノリをリズムの揺らぎで出すのではなく、細分化したビートのアクセント位置をずらすことでウネリを生み出すタイプだからね。
ただ、GaddもEddie Gomezと出会わなければ「イモな4ビートしか出来ない」と言われてたかもしれないな。この二人が揃うことでより鋭角的なノリの「新しい4ビート」が実現できたわけじゃ。
|
| ひろ子: |
「ひろQ」でもSquareなビートから4ビートに変わる曲をやりましょうよ! |
| 五反田: |
そうじゃな、それでは有名な「On Green Dolphin Street」をやってみよう。
4ビートになるところで「チンタラ」しないように気を付けてな!
|
| マイナス・ワンでのアグレッシブなベースはいったい誰? |
| つづく |