| ジャズを練習するにしても、何をどう練習したらいいかわからない、そんなひろ子に五反田博士は難題を突きつけます。 |
| 五反田: |
それじゃあ、早速何か、アドリブを弾いてもらおうかのぉ? |
| ひろ子: |
え!、そんな博士! まだ何も知らないのにアドリブなんて出来ません。 |
| 五反田: |
ひろ子くんは何を知ればアドリブを出来ると思っておるのかね?
自分の出来ること・知ってることを総動員して演奏する、これがアドリブじゃ。たとえそのアドリブがどんなに拙くてもそれがその時の自分の実力であり、自分のアドリブなのじゃよ。
その結果、「かっちょ悪いなあ」とか「おサムいプレイだな」と自分で感じれば、足りない部分を自分で見つけて練習すればいい。決して「これを知っていれば大丈夫」とか「これだけ練習しておけば十分」といったことはないのじゃ。常に「Play&Practice」の連続、「終わりなき戦い」じゃ!
|
| ひろ子: |
アドリブって厳しいんですね。 |
| 五反田: |
そう、深刻に考えられても困るんじゃが...
「どうせヘタなんだから、でたらめに弾いちゃえ!」ぐらいに開き直って演奏してみると意外と先が見えてくるものじゃよ。逆に弾かなきゃ何も始まらん。決して「これを勉強してないから弾けない」などと思わないことじゃ。
|
| ひろ子: |
はい、わかりました。 |
| 五反田: |
なんていう精神論(でもこれが一番、大切なんじゃよ。)はこれぐらいにして、技術的な話を特別にひろ子くんだけに教えて上げよう。これを知っていると「ちょっとかっちょええ」ブルースが弾けるという、「ブルーノート・スケール」というのを教えて進ぜよう。 |
| ひろ子: |
そもそも、「ブルース」ってよく聞くんですが、何なんですか? |
| 五反田: |
「ブルース」にはいろいろな意味があって説明が長くなるので、ここでは「ブルース形式」もしくは「ブルース・コード進行」に限って説明しよう。
これはジャズに限らず、Rock'n Roll、Rhythm & Bluesなどあらゆるポピュラー音楽の原点ともいえるものじゃ。例えば「Johnny B Good」や「のっぽのサリー」みたいな曲ではこんなコード進行じゃ。
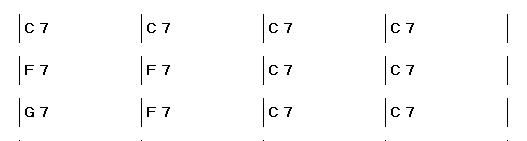
|
| ひろ子: |
「Johnny B Good」と「のっぽのサリー」は同じコード進行なんですか? |
| 五反田: |
そうじゃ。違うのはキーとテンポと歌詞と題名だと思って差し支えない。さすがにズージャの場合はこれじゃダサダサなんで、こんな風に演奏することが多い。
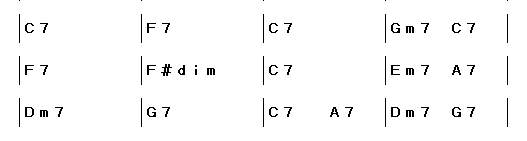
|
| ひろ子: |
ちょっとコードが増えましたね。 |
| 五反田: |
そうなんじゃ、ジャズの場合、なんでも複雑にしたがるクセがあってな。でもその反面、思いっきり単純化しちゃう場合もある。
まあ、とにかくディテールは違っても全体のサウンドや骨格は「のっぽのサリー」と同じなんじゃ。
|
| ひろ子: |
ブルースとブルーノート・スケールというのは何か関係があるんですか? |
| 五反田: |
ん〜ん、直接は関係ないと思うが、ブルースを演奏するにはブルーノートは欠かせないということは言えるじゃろうな。
じゃあ、説明に入ろうか。
これが普通のドレミファソラシドのメジャー・スケール(長音階)というやつじゃな。
|
|
|
| これの3番目と7番目を半音下げた音をブルーノートといって、これを音階にしたものをブルーノート・スケールと言うんじゃ。 |
|
|
|
| 稀にというか、割にしょっちゅう、5番目の音も半音下げるが、これはスケール上の音というより、「よりブルージー」にする装飾的なブルーノートととらえたほうがいいかもしれない。多少、アクが強いもんでな。 |
|
|
|
| もっと音数を減らして、いわゆる「よな抜き」と呼ばれる、「ブルーノート・ペンタトニック・スケール」という音階もあるんじゃ。 |
|
|
| これはストレートに音階を上がり・下がりするようなパターンで使うと効果的じゃ。 |
で、この音階だけでブルースを演奏することができる。ひとつやってみようか。これまで説明のためにキーはC(ハ長調)だったが、ここからはジャズでよくやるキーのF(ヘ長調)にするぞ。念のためにキーがFのブルースのコード進行と各スケールを載せておく。
| 普通のメジャー・スケール(長音階) |
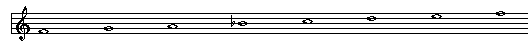 |
| ブルーノート・スケール(3度と7度がフラット) |
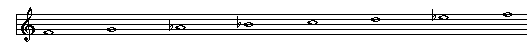 |
| ブルーノート・スケール(5度もフラット) |
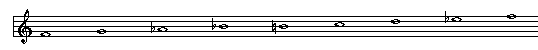 |
| ブルーノート・ペンタトニック・スケール |
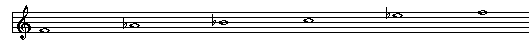 |
| ブルースのコード進行 |
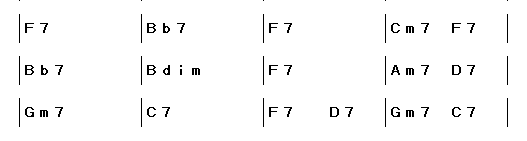 |
|
| ひろ子: |
へえ、なんかジャズっぽい雰囲気が出ますね。ブルーノートだけでもアドリブは出来るんですね。ブルーノートってブルース以外では使えないんですか? |
| 五反田: |
そんなことはないよ、どんな曲でもどんな場所でも使えるぞ。ただ、あまり多用するとワン・パターンに聞こえてしまったり、ブルーノートばっかりじゃ、サウンド・カラーが一色に限られてしまうから、ポイントを絞って使うのが効果的じゃな。
じゃあ、ひろ子くんもちょっと弾いてみたまえ。
|
| ひろ子: |
コードがいっぱい変わりますが、どうしたらいいんですか? |
| 五反田: |
今日のところはそんなの、無視じゃ。 |
| ひろ子: |
え〜え!、そんないい加減でいいんですか? |
| 五反田: |
いいんじゃ。厳密なようでいて、いい加減。これがジャズなんじゃ。 |
| ひろ子がピアノを弾く。演奏内容はちょっと内緒 |
| ひろ子: |
何となく、曲の流れというか雰囲気が今いち、掴めなくって。 |
| 五反田: |
そんな感じじゃな。では、次回までにこんな練習をしておくといいぞ。ベースが弾いていることを自分の楽器で弾くんじゃ。おい、関くん、ちょっと1コーラス、弾いてみてくれ。
これをRunningと言ったり、歩いているようなニュアンスもあるので、Walking Baseなどとも言うな。このベース・ラインを何回も何回も自分の楽器で弾いてみるんじゃ。そのうちに曲の流れが体に染み込んで、頭の中でコードが響いてくるようになるんじゃ。
ベースのRunningは最低限の音数を使ったアドリブとも言えるので、アドリブ練習にも有効だぞ。
|
| ひろ子: |
わかりました! 毎日、5時間づつ、ピアノの練習します! |
| 五反田: |
そんなに練習して、バークレーにでも行くつもりかね? |
| つづく |